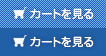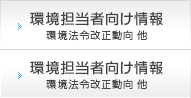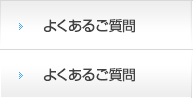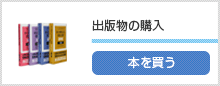- HOME
- 出版物の購入・ご案内
- 環境管理バックナンバー
- エネルギーからみた地球温暖化問題
環境管理バックナンバー カテゴリ:エネルギーからみた地球温暖化問題
キーワードサーチ
- マテリアルフローコスト会計
- 地球温暖化
- 化学物質
- カーボンフットプリント
- 京都議定書
- 公害防止
- LCA
- 生物多様性
- 水質汚濁
- 廃棄物
- リスクマネジメント
- 海外
- COP
- 土壌汚染対策法
- 環境技術移転
- セクター別アプローチ
- APP
- 大気汚染
- ISO 14001
- エコマテリアル
- 太陽光発電
- 揮発性有機化合物
- 森林資源
- 水ビジネス
- 省エネルギー
- GSEP
- クリーン開発メカニズム
- スマートグリッド
- ナノ
- 地下空間
- 環境マネジメントシステム
- ISO/TC207
- REACH規則
- バイオマス
- 有害物質
- 水銀
- 3R
- CCS
- IPCC
- MFCA
- エコラベル
- ポリ塩化ビフェニル
- リサイクル
- 排出量取引
- 風力発電
- 放射性廃棄物
- 騒音・振動
- 審議会
バックナンバーの閲覧 / 冊子版の購入
- 協会会員の方は、記事全文をPDFファイルで閲覧ができます。
ログインしてご利用ください。 - 各号の概要の閲覧、冊子版の購入はどなたでも
ご利用いただけます。
-
<シリーズ>【エネルギーからみた地球温暖化問題シリーズ53】日本の脱炭素戦略の不整合──省エネ法の改正を考える
竹内 純子(NPO法人 国際環境経済研究所 理事/主席研究員) ▼概要文表示2021年7月号 -
大幅な脱炭素化に向けてのセオリーは、電源の低炭素化と需要の電化の同時進行である。電源構成に対する関心は高く、FIT制度に象徴されるようなゼロエミッション電源の拡大に向けた政策的支援も手厚い。一方で需要側の転換に向けた議論は、消費者の行動変容と言った「気持ち」の議論に陥りがちで戦略的観点が不足しているのではないかという問題意識を筆者は持っている。政策的にも電化を阻害する制度が存在し、政策的方向性の不一致がみられる。その象徴がFITによる再エネ発電賦課金だ。再エネの環境価値に対する対価として支払われる再エネ発電賦課金は、電気にだけかかる炭素税だ。電気料金単価は会社やメニューによって異なるものの、約20円/kWhと仮定すると、賦課金の3.36円/kWhは約15%にもなる。それがさらにこれから増えていくこと踏まえ、電力需要を減らし賦課金の掛からない化石燃料に転換する計画を立てている企業の話も耳に挟む。電気だけに賦課金をかけることで、化石燃料の消費を続ける、あるいは増やすことに誘導してしまっている。再エネ発電賦課金に加えて電化の阻害要因となっているのが「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」(以下、省エネ法)である。省エネ法は、再エネ電気を契約している需要家であっても“化石燃料により発電された電気”として報告することになっており、電源構成の変化や選択肢の多様化を柔軟に反映できない制度だ。省エネ法の致命的欠陥を早急に正さなければ、むしろ再エネ発電と電化の普及阻害要因となる懸念がある。本稿では、産業の現場などにおける温暖化対策の主要な規制である省エネ法の時代遅れを是正し、本来の機能を果たせるようになるにはどのような改善が必要であるかを検討したい。
-
<シリーズ>【エネルギーからみた地球温暖化問題シリーズ52】「ゼロカーボンシティ」に向けて必要なこと
竹内 純子(NPO法人 国際環境経済研究所 理事/主席研究員) ▼概要文表示2021年6月号 -
政府が2050年のカーボンニュートラルを掲げるのに先んじて、環境省の呼びかけに応じて多くの地方公共団体がゼロカーボンシティ宣言をしており、その数は本年5月20日時点で388に上る。地球温暖化対策の推進に関する法律では、「都道府県及び市町村は、その区域の自然的社会的条件に応じて、温室効果ガスの排出の抑制等のための総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施するように努めるものとする」ともされていることに加えて、市民・消費者の生活に身近な存在として地方公共団体が果たすべき役割は大きい。しかし、エネルギー需要の構造はそれぞれの地域の気象条件やライフスタイル、産業構造などによって大きく異なる。また、供給側についても今後増加すると見込まれる再生可能エネルギーのポテンシャルは自然条件に大きく左右されるうえ、既存のエネルギーインフラとして都市ガス導管が通っているのかいないのか、あるいは、港湾を保有し外部からのエネルギー資源へのアクセスが比較的容易に確保できるのか、といった様々な条件によって描ける未来は変わってくる。それぞれの地域の実態をよく把握し、戦略的に考える必要があるが、それぞれの地域でエネルギー転換に必要な知見を有する人材を確保することも難しい。今回は、2050年ゼロカーボンシティを宣言した自治体が考慮すべきことの視点を整理したい。
-
<シリーズ>【エネルギーからみた地球温暖化問題シリーズ51】日本の水素戦略の展望と課題── 2050年カーボンニュートラルの柱は電化・水素化
竹内 純子(NPO法人 国際環境経済研究所 理事/主席研究員) ▼概要文表示2021年4月号 -
昨年12 月、「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」が公表された。総花的である、あるいは、具体性がないといった批判の声も多く聞くが、30年後のカーボンニュートラルという壮大なチャレンジにはあらゆる技術の総動員が必要であり、その中で、脱炭素化に向けた戦略の柱として、電力部門の脱炭素化と電力部門以外(一部の燃料・原料。実質的に需要家側の対策)での「電化・水素化」が明確に掲げられたことは評価できると筆者は考えている。特に重要なのは、需要対策の重要性を謳ったことであり、これまでのエネルギー政策が供給対策に偏っていたことを鑑みれば、大きな政策転換と言えるだろう。供給側と需要側の対策を車の両輪に例える筆者からすればまだ需要側の議論が手薄であることは指摘せざるを得ないが、それでもこの変化を歓迎したい。しかし、今後この戦略を実装に向けた取り組みにブレークダウンしていかねばならない。こうした状況を受けて、現在、筆者が委員を拝命している経済産業省の水素・燃料電池戦略協議会では、水素技術に関わる企業に広くその技術展望やコスト見通し、必要とする政策的措置など幅広くヒアリングも行ったうえで、次期エネルギー基本計画や水素基本戦略の見直しを見据えて、議論を加速させている。戦略の中間とりまとめがみえてきたところで、改めて、わが国の水素戦略の展望と課題を整理したい。
-
<シリーズ>【エネルギーからみた地球温暖化問題/第50回】2021年初の電力需給ひっ迫と価格高騰の経験に学ぶべきこと──電力システムの再構築の必要性
竹内 純子( NPO 法人 国際環境経済研究所 理事/主席研究員) ▼概要文表示2021年3月号 -
昨年秋より、わが国の電力システムの課題を問いかける事象が続いている。将来の供給力維持・確保を目的とした容量市場の第1回入札が行われ、菅首相による2050年カーボンニュートラル宣言、年末から年始にかけての電力需給ひっ迫と卸市場(JEPX)の高騰、さらに寒波に襲われた米テキサス州の電力価格急騰と輪番停電、福島県沖地震による関東圏の大規模停電など、電力供給システムの健全性を維持しつつ改革を進めることの難しさを思い知らされる事象が相次いだ。今回は、わが国における電力需給ひっ迫から何を学ぶべきなのかを考えてみたい。
-
<シリーズ>【エネルギーからみた地球温暖化問題/第49回】容量市場の問題から考える、電力システム改革の再定義
竹内 純子(NPO法人 国際環境経済研究所 理事/主席研究員) ▼概要文表示2021年1月号 -
電力システムはその国や地域による特徴やそのときの社会状況、資源の調達などの諸条件によって制度設計がアレンジされなければならない。米国の経済学者であるRobert Wilsonが「自由化された電力市場の中には、2 つとデザインが同じものはない。大規模な実験が進行中であり、比較研究から学ぶことができる」としている通りだ。電力市場の自由化に乗り出したからには、こうした試行錯誤を積み重ね、より良くする努力が不可欠であり、逆にいえば、そうした努力に対する覚悟もなくシステム改革に着手することは許されざることなのだろう。そうした意味で、わが国がシステム改革の中で安定供給をどのように確保するかについて議論を呼ぶ容量市場を巡る議論について論じてみたい。2020年9月14日、日本における容量市場の第1 回メインオークションの結果が、電力広域的運営推進機関(OCCTO)より公表された。正直にいえば当初筆者は、容量市場の議論がこれほど注目を集めるとは思っていなかった。オークションの約定価格が上限価格近くの高値(14,137円/kW)となったと聞いたときには多少の驚きは感じたものの、それはそれで今の市場からのメッセージであると受け止めたし、それ以前の問題として、わが国の容量市場には「経過措置」と称する特殊なローカルルールが設定されており、落札された電源の多くがこの金額の約6割を受け取るにすぎないということが頭にあったからだ。しかも、再エネ賦課金のように毎年継続的なものではなく、4年後の2024年の1年間に限る話なので、電源側からみてそれほど期待値の高い制度でもなかった。実際、その後資源エネルギー庁から公開された資料によれば、2010年度末以前に建設された電源の容量確保契約金額に対しては、経過措置として42%の控除率が課されるので、落札された電源等(DRなども含むため、電源「等」と表現されている)の約78%が受け取るのは8,199円/kWである。その金額の妥当性は発電所の条件によっても異なるが、後述するように、中立的監督機関である電力・ガス取引等監視委員会の調査によれば、限界電源がいまスポット市場や調整力としての対価などで得ている収入はわずか424円/kWしかないのに対し、税金や人件費、メンテナンスコストなど含めた維持管理コスト平均値は12,262円/kWになるとされる。赤字幅が縮小されて良かったと感じた電源は多くあっただろうが、これまでの歪んだ状況に改善が施されたというに過ぎない。しかし、支払う側の新電力事業者からすればそのようなのんきな話ではなかったのも確かだろう。一般紙にも記事が掲載され、一部には「容量市場は石炭火力・原子力温存策であり、再エネへのエネルギー転換を遅らせるもの」といった批判的な論調が先行するなど、注目度は高まっていった。そうした議論を見聞きしているうちに、この問題は、電力システム改革において我々が何を実現したいのかといった価値観にもかかわる課題であると認識するに至った。そのため、筆者がエネルギー産業に関わるエコシステムを豊かにしたいと2018年10月に創設した合同会社であるU3Innovationsで、異なる立場の方のご意見を伺う座談会の場を設けた。その議論は今も弊社のウェブサイトで公開中なので、ぜひ直接ご覧いただきたい。そこでの議論も踏まえたうえで、この問題が投げかける意義について、筆者なりに考えてみたい。
-
<シリーズ>【エネルギーからみた地球温暖化問題/第48回】デフォルト化した「2050年温室効果ガス排出実質ゼロ」を巡る現状整理
竹内 純子(NPO法人 国際環境経済研究所 理事/主席研究員) ▼概要文表示2020年12月号 -
世界の低炭素化・脱炭素化に向けた動きが加速し続けている。2020年以降の国際枠組みであるパリ協定は、各国に目標の達成を法的に義務付けるものではなく、各国が協定のもとに提出する削減目標も正確には「自国が決定する『貢献』(Nationally Determined Contribution:NDC)」と表現されている。二大排出国である米国・中国の参加を得るには法的削減義務を課す枠組みとすることはできず、義務化しないというレッドラインを死守することでパリ協定は誕生したのである。このことはパリ協定が採択された当時すでに本誌でも指摘していた通りであり、「いい加減な仕組み」との批判も多くある一方、「良い加減」にとどめることで京都議定書の失敗を繰り返さないようにしたともいえるだろう。しかしパリ協定で掲げられた長期目標達成との整合性を重視し、欧州では気候法(Climate Law)によって、2050年までにすべてのEU加盟国が気候中立国になることに法的拘束力を持たせるなど、義務化を進める動きもある。また、中国が2060年の、日本や韓国が2050年のネットゼロを目標として掲げた。さらに、政府がビジョンを掲げるだけでなく、経済活動の最重要インフラの一つであるファイナンスが気候変動を強く求めるようになっている。資本主義社会の血液とも表現される資金の流れが変われば、社会の方向性は変わる。各国のコミットメントや金融・投資の変化により、もはやデフォルト化した2050年ネットゼロを巡る現状について整理したい。
-
<シリーズ>【エネルギーからみた地球温暖化問題/第47回】 エネルギー基本計画改定に向けた提言
竹内 純子(NPO法人 国際環境経済研究所 理事/主席研究員) ▼概要文表示2020年11月号 -
政府は総合資源エネルギー調査会において、次期エネルギー基本計画策定に向けた議論を開始した。エネルギー基本計画は閣議決定もされるとはいえ、定性的な文章に過ぎない。霞が関的に微妙なグラデーションはつけられているものの、必要な施策が列記されているものだ。しかしここに書き込まれるかどうか、どのような表現で書き込まれるかによって、政策的支援の厚みも変わるので、基本計画を反映し具体的な数字に落とし込んだ「長期エネルギー需給見通し」も含めて、エネルギー事業者の関心は高い。しかし、そもそもわが国は電力・ガス事業のシステム改革を進め、市場原理を導入した。自由化した市場において、政府が1%刻みの需給見通しを描き、事業者がそれを固唾を飲んで見守るという構図には違和感を覚える。エネルギー供給の重要性はどのような制度設計の下でも変わるものではないが、自由化した時点で政府の役割についても見直すべきだったのではないだろうか。また、時間軸も今まで通り10 年後を議論すればよいわけではないだろう。第5次エネルギー基本計画は2030年の議論をしたものであり、2050年はイノベーションへの期待から、非連続な未来とされた。しかし、菅首相が2050年実質ゼロを目指すことを表明するとも報じられており、もはや2050年までを視野に入れ一連のシナリオを描くべき時期になりつつある。一方で、裏付けをもって2050 年実質ゼロのエネルギーミックスを提示することは不可能だ。では何を政府は示すべきなのだろうか。エネルギー基本計画改定に向けた議論の中で持つべき視座は何かを整理し、これから本格化する議論への提言としたい。
-
<シリーズ>【エネルギーからみた地球温暖化問題/第46回】エネルギー供給の強靭化に向けて――台風10号対応の振り返りと強靭化法、スマートレジリエンスネットワークについて
竹内 純子(NPO法人 国際環境経済研究所 理事/主席研究員) ▼概要文表示2020年10月号 -
9月初旬に九州を縦断した台風10号は、「経験したことのない規模」であるとして、列島は異様な緊張感に包まれた。9月6日夕方から開催された関係閣僚会議で安倍前首相が、「直ちに命を守る行動をとってほしい」と呼び掛け、9月7日朝7時には、九州・中国・四国地方の876万人に避難指示・避難勧告が出され、実際に避難された方も17 万6,000 人に及んだ。亡くなられた方、浸水等の被害を受けられた方にまず、心からお悔やみとお見舞いを申し上げたい。これだけの規模の台風ということで、電力の安定供給についても懸念する声が強くあった。九州地域の停電件数は、9月7日早朝6時頃に最大(475,910戸)となり、同社区域内の供給世帯数全体の約5.6%に上った。正直に言えば筆者は、この規模の台風であれば、平成3年の台風19号(九州全土で約200万戸)、平成16年の台風18号(同じく九州全土で約100万戸)などと同程度の被害が発生することも危惧していた。47万戸の停電は決して小さくはないが、しかし、復旧作業はかなり迅速に進んだと評価できることが、各方面へのヒアリングや分析でわかってきた。本稿では、台風10号における電力供給確保がどのように進められ、そこから学ぶことは何か、また、今年2月成立したエネルギー供給強靭化法の意義と課題、そして、レジリエンス向上を目的とした民間事業者の取り組みを紹介したい。
-
<シリーズ>【エネルギーからみた地球温暖化問題/第45回】石炭火力発電所の廃止問題に関して検討すべきこと
竹内 純子(NPO法人 国際環境経済研究所 理事/主席研究員) ▼概要文表示2020年8月号 -
7月2日に、読売新聞が朝刊一面で、その後メディアが一気に追随して報じた、石炭火力発電所の廃止。翌日、梶山経済産業大臣が閣議後の記者会見で、2018 年に策定された第5 次エネルギー基本計画に書かれている「非効率な石炭火力(超臨界以下)に対する、新設を制限することを含めたフェードアウトを促す仕組みや(中略)等の具体的な措置」について検討を始めるよう指示したことを明らかにしている。わが国のエネルギー政策の基本方針たる「エネルギー基本計画」が言いっぱなしであることは許されず、実現するための政策措置を講ずべきことは論を俟たない。エネルギー政策の所管である経済産業省が、2030 年に向けた長期エネルギー需給見通し実現に向け本腰を入れて取り組むことは、大いに歓迎したい。しかしわが国のエネルギー政策の現状や経緯を踏まえると、様々な懸念点があることも確かだ。報道が先行したことが原因かもしれないが、疑心暗鬼になっている関係者も多い。透明性を持って政策議論を重ね、国益・地球益にかなう制度設計になることを切に祈る次第である。本稿では、政府が表明した石炭火力発電所の廃止を巡る課題や懸念を書いてみたいと思う。ただし気候変動対策の重要性は高まる一方であり、エネルギー基本計画を言いっぱなしにしないのは政府の当然の責務でもある。非効率石炭火力発電のフェードアウトそのものが腑に落ちないといっているわけでは決してないことを最初に申し上げたい。
-
<シリーズ>【エネルギーからみた地球温暖化問題/第44回】わが国のインフラ海外展開を考える
竹内 純子(NPO法人 国際環境経済研究所 理事/主席研究員) ▼概要文表示2020年6月号 -
わが国はこれから、何を売って食べていく国になるのだろうか。これまで長いこと、「日本は工業立国であり、付加価値の高い工業製品を輸出して貿易黒字を維持している」といわれてきた。実際、2011年に貿易赤字に転落するまで、1980年から30年近く、輸出が輸入を上回る貿易黒字の状態が続いていた。内需が伸び悩む中で、外で稼ぐことの重要性は増しているが、新興国企業の価格競争力と技術力の向上も顕著で、わが国が今後何を成長の原動力にしていくかの議論が急がれている。わが国の成長を考えるなかで重要な視点が、世界の持続可能な発展に貢献するということであろう。特に新興国・途上国はまだ社会インフラがまだ整っておらず、そのインフラ整備をどう進めるかで社会が持続可能な発展を遂げられるかどうかが大きく変わってくる。わが国企業がそこに貢献することを目指して政府は、2013年4月に「経協インフラ戦略会議」を設立し、2020年には年間30兆円の受注をするという目標を掲げた。2018年には「海外インフラ展開法」を制定し、国土交通大臣が定める基本方針の下で、官民連携して日本企業の参入を強化していく体制を整備している。2020年以降の目標を策定し新たな戦略を立案するため、総理大臣補佐官の下で「インフラ海外展開に関する新戦略策定に向けた懇談会」を設置して検討を進めるとともに、実際に何を売りとするのか、必要な施策等についてより具体的に議論するために経済産業省貿易経済協力局が事務局となり「インフラ海外展開懇談会」(以下、海外展開懇談会)が設置され議論が行われている。海外展開懇談会では、議論が必要な分野としてエネルギー・電力とデジタルの二つを挙げており、筆者はそのエネルギー・電力分野の議論に委員として参画する機会を得た。公表された中間とりまとめをご紹介するとともに、わが国の海外インフラ展開に関する筆者の私見を述べたい。
-
<シリーズ>【エネルギーからみた地球温暖化問題/第43回】Beyondコロナの気候変動問題
竹内 純子(NPO法人 国際環境経済研究所 理事/主席研究員) ▼概要文表示2020年5月号 -
先月号の原稿を書いていたときには、ここまで新型コロナウイルス感染が拡大し、私たちの行動変容が必要になってくるとは想像できていなかった。この1か月、いや、数週間で状況は急速に悪化し、我々の日常も大きな制約を受けることとなった。今は読者の皆さまの健康をお祈り申し上げるとともに、医療・介護従事者をはじめとしてそれぞれの持ち場で奮闘されている方々に心からの感謝を捧げたい。これまでの景気後退と異なり、消費が瞬間的に蒸発したと表現されるこの新型コロナウイルスによる経済危機。いま企業経営者の関心は、自粛期間の事業継続と、その後長く続くと予想されるwithコロナ時代をどう生き抜くかに集中しており、直前まで世界が直面する課題として日々メディアに取り上げられていた気候変動問題はめっきり影をひそめてしまっている。日々感染者数、死亡者数が増加し、「第三次世界大戦」にも例えられる危機的局面にあっては当然の反応であるし、CO2削減について議論するまでもなく、経済が停止したことで各国の排出量は激減している。しかし我々の社会はこの仮死状態から必ず立ち上がらなければならない。その際に気候変動問題は、社会にとってどのように捉えられるのであろうか。どのような社会になっているかを描くことは誰にもできないが、その景色が今までとは全く違うものになっていることだけは確かだ。against、with、afterとコロナウイルスとの付き合い方も変遷していくと思われるが、少なくともこの混乱期を超えたあとに気候変動問題がどのように扱われるのか、今ある情報の整理を試みたい。
-
<シリーズ>【エネルギーからみた地球温暖化問題/第42回】原子力イノベーションは進むのか――米国を例に考える大規模技術開発支援
竹内 純子(NPO法人 国際環境経済研究所 理事/主席研究員) ▼概要文表示2020年4月号 -
わが国の原子力発電事業には厳しい状況が続いている。本年1月17日には四国電力伊方発電所3号機の運転差止めを命じる仮処分決定が出された。3 月16 日には九州電力の川内原子力発電所がテロ対策施設設置の遅れを理由に停止する。わが国の原子力事業を巡る不透明性は全く改善されず、行くことも退くこともできない状態に追い込まれているようにみえる。一方、世界は原子力技術とどのように向き合おうとしているのだろうか。本誌2019年4月号に寄稿した「原子力をめぐる“世界の潮流”──各国の動向整理と米国・英国の政策」では、米国や英国の原子力政策を整理したが、高まるエネルギー需要や低炭素化への要請から、東欧やアジアなどで多くの国が原子力発電所の導入や技術開発を進めている。広がりをみせる原子力利用と技術開発について整理した上で、米国を例に原子力イノベーションのあり方を考えたい。
-
<シリーズ>【エネルギーからみた地球温暖化問題/第41回】気候変動国際交渉を巡る三つの乖離――COP25を終えて考える、温暖化問題に「本当に必要なこと」
竹内 純子(NPO法人 国際環境経済研究所 理事/主席研究員) ▼概要文表示2020年2月号 -
昨年12月、スペインのマドリッドで開催されたCOP25は、12月15日(日)まで延長され閉幕した。正式な会期である2週目の金曜日までに議論が終わらないのは毎年のことなので、筆者は余裕をみて14日(土)に現地を発つ旅程にしていたが、それでも最終決着はみられなかった。筆者の記憶が正しければ、日曜日まで延長するのは南アで開催されたCOP17以来であり、これまでで最長の会期となった。交渉しなければならなかった論点がほぼパリ協定第6 条の運用ルールのみであることを考えれば、この国連交渉プロセスの非効率性と、合意を得ることの難しさは以前にも増しているようにも思われる。そもそもCOPの役割は、パリ協定の採択・発効により大きく変質したと考えるべきだろう。パリ協定の下では、各国は「自国で決定する貢献(Nationally Determined Contribution:NDC)」という削減目標を掲げる。京都議定書の下では、各国の目標が交渉を経て決められたが、パリ協定は各国の自主性を前提とする枠組みである。パリ協定の締約国は、NDCを作成して国連事務局に提出し、その後達成に向けた国内対策をとることを義務づけられている。条約事務局は5年ごとに全体の進捗を評価する「グローバル・ストックテイク」を行い、各国はこれを踏まえて5年ごとにNDCを再提出することが義務づけられているが、評価の仕方などに関するルールも策定されてしまえば、あとは運用に委ねられることとなる。そうなると、COPで何が交渉されるのか。詳細ルールについての議論はまだ少し残るものの、その役割を既に変えつつある。COP25の会場内外の雰囲気や議論の流れをお伝えしつつ、雑感的にまとめてみたい。
-
<シリーズ>【エネルギーからみた地球温暖化問題/第40回】EUの気候変動金融ベンチマークに関する議論の進展──欧州委員会TEGの最終レポートを読む
竹内 純子(NPO法人 国際環境経済研究所 理事/主席研究員) ▼概要文表示2019年11月号 -
本連載で毎月関連記事を書いている通り、欧州委員会は着々とサステナブル・ファイナンスについて検討を進めている。2016年末に組織したハイレベルの専門家グループ(HLEG:EU High-Level Expert Group on Sustainable Finance)から出された最終報告をもとにアクションプランを策定、2018年5月には規則案(「持続可能な投資を促進するための枠組みの構築に関する規制案」)、改正指令案(「持続可能な投資及び持続可能性のリスクに関する開示の規制についての提案及び指令(EU)2016/2341の改正案」) を公表している。その後、さらなる議論の場として技術専門家グループ(TEG:Technical Expert Group in Sustainable Finance)を設立して、そのTEGがタクソノミー等の検討を進めていることは、既に本誌8 月号の「EUタクソノミーに関する議論の進展── 欧州委員会TEGのテクニカル・レポートを読む」等でもご報告した通りだ。欧州委員会は、①分類システムの確立(タクソノミー)、②機関投資家がESG要素をリスク・プロセスに組み込む方法に関する開示要件の改善、③投資家が自らの投資によるCO2排出量を比較するのに役立つベンチマーク作成、という三つの提案をパッケージで提示しており、TEGはテーマに応じてサブグループを設立して検討を進めている。それらの検討は相互に関連しあうものであり、全体を俯瞰する必要がある。このうちの「ベンチマーク」について、TEGは2019年6月に中間報告を、9月には最終報告を公表している。この「Report on Benchmarks」(以下、最終レポート)を概観することで、欧州で進むサステナブル・ファイナンスの議論のフォローを続けたい。
-
<シリーズ>【エネルギーからみた地球温暖化問題/第39回】金融機関の炭素関連資産情報開示と気候関連リスクのストレステストについて
竹内 純子(NPO法人 国際環境経済研究所 理事/主席研究員) ▼概要文表示2019年10月号 -
これまで本誌に連続して寄稿しているとおり、金融・投資の関係者が気候変動を新たなリスクとして認識し、金融市場の投資判断基準に気候変動に関する価値観を取り込む動きが活発になっている。あるいは、リーマンショックを経験した金融市場が、気候変動が引き金となって金融危機につながる可能性を懸念し、情報開示を求めていると表現したほうが正しいかもしれない。金融安定化理事会(FSB)が民間有識者によるタスクフォース(TCFD)を設置し(2016年2月)、その最終報告書がG20 首脳会議に報告されたこと(2017年3月)は、関係者にこの動きが本物であることを認識させたといえるだろう。TCFDが求める情報開示に応じる企業も急速に増加している。しかし、TCFDの最終報告書にも「さらなる作業が必要な分野」についての記載がある通り、まだ議論の途上であり、多くの懸念点があることは2017年3月号の本誌に寄稿した「続・気候変動を動かす金融・投資の動き―─TCFDの提言案を読む」でも述べた通りである。特にTCFDが銀行など金融部門に対して開示を推奨している炭素関連資産比率はGICS( Global Industry Classification Standard:世界産業分類基準)に基づくもので、セクター次第というところが大きい。各企業の努力というより、どんな業種かで評価されてしまう、いわば「雑なブラウンタクソノミー」ともいえる。これでは、どのように情報開示を進めればよいのか、迷う向きも多いだろう。しかし実は、本年7月にわが国のメガバンク3行が統合報告書のなかで、TCFDが求める炭素関連資産の数字を公表している。本稿前半では、TCFDの提言する炭素関連資産の公表について、わが国のメガバンク3行がどのように対応しているのかを整理する。また後半では、オランダ中央銀行が昨年10月に公表した、気候変動リスクに関わるストレステストに関するoccasional studyの概要をご紹介する。これらの動きから、金融機関の中で急速に進む、特定の産業のエクスポージャーの比率の公表を求める動きについて考える。
-
<シリーズ>【エネルギーからみた地球温暖化問題/第38回】サステナブル・ファイナンスと銀行の自己資本比率規制──金融規制に対するEUタクソノミーの波及を考える
竹内 純子(NPO法人 国際環境経済研究所 理事/主席研究員) ▼概要文表示2019年9月号 -
これまでESG投資は、基本的に自主的な取り組みとして成長してきた。国連大で投資判断に社会的責任の要素を加味していくことを求めた「責任投資原則( PRI:Principles for Responsible Investment)」や、企業等に質問票を送付し、それによって得た非財務情報を評価・公表する活動を続けるCDP(旧Carbon Disclosure Project)などの動きは、いずれも公的年金基金や民間企業に対して自主的な取り組みとしてESGの観点を求めてきたものである。しかし、いわゆる「2℃目標」および今世紀後半のカーボン・ニュートラルを長期目標として掲げるパリ協定が採択・発効したことを受けて、欧州連合がサステナブル・ファイナンスの法制化に向けた議論を進めている。法制化するとなると、「何がgreenか」、「何がサステナブルか」を金融機関や投資家の自主的な判断に委ねるのではなく、サステナブルな経済活動を特定する際に役立つ統一的な分類を示すことが必要となり、現在議論が進められているのが、これまで何度もお伝えしてきている「タクソノミー(分類学)」だ。当初欧州委員会が想定していたタクソノミーの位置づけは、グリーンな活動を例示するポジティブ・リストであった。欧州委員会が策定した枠組規則案もその方針に沿っており、現在議論されているタクソノミーはこの考え方で落ち着く可能性が高い。しかし、ポジティブ・リスト方式では、2℃やカーボン・ニュートラルの達成に向けて十分ではないとして、環境適合性が低い活動の分類であるネガティブ・リストを求める声も出てきている。将来的には、タクソノミーはグリーンとブラウン両方を定める形になるかもしれない。整備されたタクソノミーは、欧州域内の金融商品の基準や、欧州の金融機関の健全性要件(prudential requirement)に反映される見込みだ。しかし、欧州域内にはとどまらず、銀行の健全性を定めるバーゼル規制に反映され、国際取引を行う金融機関全体に波及する可能性もある。前号「EUタクソノミーに関する議論の進展── 欧州委員会TEGのテクニカル・レポートを読む」で述べた通り、2019年末までに欧州委員会の技術専門グループ(Technical Expert Group:TEG)は、技術的スクリーニング基準を精緻化し、タクソノミーの利用に関わるガイダンスを開発することを予定している。議論に残された時間は少ない。本稿では、タクソノミーの位置づけや用途、特に銀行の健全性要件を定めるバーゼル規制との関連について、議論の動向を追う。
-
<シリーズ>【エネルギーからみた地球温暖化問題/第37回】EUタクソノミーに関する議論の進展── 欧州委員会TEGのテクニカル・レポートを読む
竹内 純子(NPO法人 国際環境経済研究所 理事/主席研究員) ▼概要文表示2019年8月号 -
これまで何度かご紹介してきたEUのタクソノミーについて、6 月18日に一つの進展があった。欧州委員会の技術専門グループ(Technical Expert Group:TEG)がテクニカル・レポートを公表したのだ。400ページを超える大作である上に、そもそもEUの政策決定プロセスの複雑さもあって、このレポートがどういう位置づけであるかわかりづらい。このレポートが公表されたこと自体、日本ではあまり報じられてもいないが、昨年5月に欧州委員会が公表した「持続可能な投資を促進するための枠組み規則」を具体化させる重要なレポートである。また、欧州の政策を理解するには決定に至るまでの議論のプロセスをみておく必要があることは、本誌読者の皆さまにはご承知の通りである。今回はEUの立法プロセスを把握し、タクソノミーに関わる議論の進捗具合を整理した上で、欧州委員会のTEGが公表したテクニカル・レポートを概観する。
-
<シリーズ>【エネルギーからみた地球温暖化問題/第36回】気候変動に関する情報開示を求める株主提案はどこまで認められるのか──エクソン・モービルに対する株主提案を例に考える
竹内 純子(NPO法人 国際環境経済研究所 理事/主席研究員) ▼概要文表示2019年6月号 -
ESG投資にはいくつかの類型があるが、株主として企業と対話し影響力を行使する中で長期的な成長を促していくエンゲージメントは、ある意味「ESG投資の本流」といえるだろう。エンゲージメントの手法にもいくつかあるが、投資家と投資先企業の直接的対話や、株主としての議決権行使などが挙げられる。後者の議決権に関する制度として、わが国が株主に議題・議案の提案を認める株主提案権を導入したのは1981 年のことであるが、経済産業省が公表した「価値協創のための統合的開示・対話ガイダンス」などにみるように、これをさらに活性化させ、企業と投資家の質の高い対話やエンゲージメントにより企業の競争力や収益力を高めようとする動きは最近ますます高まっている。GPIFによる調査によると、日本版スチュワードシップ・コード改訂以降のIRミーティング等における機関投資家の変化について、4割の企業が「好ましい変化」と回答するなど、企業と投資家の対話を促進する動きは企業にも前向きに受け止められていると考えられる。しかしそもそも株主提案権の適正な利用についてはまだ模索が続いている段階であり、それが気候変動という地球規模かつ長期的な課題で、不確実性の高いテーマにおいて活用されることには問題も指摘されている。具体的には、気候変動に強い関心を寄せる海外機関投資家がオイルメジャーなどのエネルギー関連企業やGAFAと呼ばれる巨大企業に対して提出した決議案について、企業からの申し立てに基づき米国証券取引委員会(以下、SEC)が一部事例については委任状勧誘資料への記載から排除できるとの見解を示す事例も出てきている。気候変動を巡る企業と投資家の対話はどのようになされるべきかは単純ではないテーマであり、わが国が株主総会シーズンを迎えるのを前に、この問題について考えてみたい。
-
<シリーズ>【エネルギーからみた地球温暖化問題/第35回】原子力をめぐる"世界の潮流"――各国の動向整理と米国・英国の政策
竹内 純子(NPO法人 国際環境経済研究所 理事/主席研究員) ▼概要文表示2019年4月号 -
ゴールデンウイークも近づき、太陽光発電の出力制御がメディアを騒がせている。特に原子力が再稼働した九州で出力制御が行われる可能性が高いことから、再エネと原子力が対立軸であり、二者択一であるかのように議論されることも多い。しかし世界全体でみれば電力需要は今後急増することが確実であるし、国内も電化・電脳化の進展により、電力需要は増えることが想定される。電力供給の安定的維持を考えれば、電力需要(kWh)だけでなく、kWあるいはΔkWという価値も必要であるため、少なくとも今世紀半ばにおいては、再エネか原子力かではなく、再エネも原子力も、加えて火力発電も一定程度は必要とされる。捨てられる技術はなく、それぞれをより高めていかなければならないというのが現実ではないだろうか。しかし原子力事業を取り巻く環境が厳しいことも事実だ。福島原子力発電所事故は安全性への疑念を与え、諸外国でも規制が見直され、安全対策コストの増加につながっている。加えて、自由化された市場においては原子力発電に対する新規投資は期待できず、西側諸国の商用軽水炉事業は困難に直面している。わが国では明確な原子力政策が示されないまま時間が経過しているが、諸外国では現在どのように原子力技術と向き合おうとしているのであろうか。状況を概観し、自由化した電力市場での原子力投資促進に向けた政策的措置を講じている米国、英国の現状を詳しくみてみたい。なお、エネルギー政策は各国それぞれの事情があり、他国の挙動を過度に気にすることには意味がないという筆者の従来の主張に変わりはない。しかし各国の原子力政策は、国家戦略の一つとして、冷静に事実を把握する必要があると考えるものである。
-
<シリーズ>【エネルギーからみた地球温暖化問題/第34回】 GPIFが採用したS&Pのカーボン・エフィシエント指数にみるESG投資の課題
竹内 純子(NPO法人 国際環境経済研究所 理事/主席研究員) ▼概要文表示2019年3月号 -
これまで本誌に何度も寄稿してきた通り、金融・投資にESGの視点を盛り込むべきという論が高まっている。そうした論の高まりにつれて、欧州や米国に比べて、わが国を含むアジア各国ではまだまだ発展途上であるとの批判も強まっている。しかし、世界最大の機関投資家であるGPIFが2015 年にPRI(国連責任投資原則)に署名し、わが国でもESG投資が急速に市民権を得つつある。そのGPIFが2018年9月にS&Pの「カーボン・エフィシエント指数」の採用を発表した。カーボン・エフィシエント指数とは、TOPIXなどの親指数をユニバースとし、 環境情報の開示状況と炭素効率性(売上高当たりの炭素排出量)を参照した調整を行って、各銘柄のウェイト(構成比率)を決定する指数である。「同業種内で炭素効率性が高い( =温室効果ガス排出量/売上が低い)企業の投資ウェイトを高く、 炭素効率性が低い企業の投資ウェイトを低く抑えた指数 」であり、「企業自ら温室効果ガス排出量の開示を行っている企業のウェイトを高めるルールが採用されており、情報開示を促進する仕組みが組み込まれている」とある。GPIFは国内株・外国株合計で1. 2 兆円について、このカーボン・エフィシエント指数に基づく運用を開始したと発表している。GPIFの運用資産総額は約150. 6 兆円(2018年12月)であるので、ポートフォリオのごく一部ではあるが、ESG投資の推進に弾みがつくと期待されている。しかし、長く気候変動問題を考えてきた立場からすると、この指数にはいくつかの課題もみえる。これまでも繰り返し述べている通り、ESG投資の主旨には筆者は賛同している。低炭素化に向けた長期的な技術開発や社会変革に取り組む企業に民間の資金が提供されなければ、気候変動問題の解決が不可能であることは論を俟たない。また、「伊藤レポート」にもある通り、持続的低収益性のパラドックスから抜け出すためには、資本効率性向上による企業価値向上に加えて、企業と投資家の対話を促進することが必要であり、ESGの視点を取り込むことで、省エネ等に強みを持つ日本企業の価値が顕在化できればと期待もしている。しかし主旨は良くとも、詳細設計が甘いと意図とは逆の結果をもたらしてしまう。GPIFが採用したカーボン・エフィシエント指数にどのような課題が隠れているのかを考え、より良いESG投資の議論に向けた出発点としたい。
-
<シリーズ>【エネルギーからみた地球温暖化問題/第33 回】COP24でみた、気候変動を動かす金融・投資の動き
竹内 純子( NPO 法人 国際環境経済研究所 理事/主席研究員) ▼概要文表示2019年2月号 -
2018年12月、国連気候変動枠組み条約締約国会議(COP24)がポーランド南部の都市カトヴィツェで開催された。今回の会議に課せられたミッションはパリ協定の実施ルールに合意することであり、難産ではあったもののそれが達成されたことは既に報道等で皆様もご承知であろう。パリ協定が温暖化対策として実効性を持ちうるのかといった懸念や、隙あらば顔を出す先進国と途上国の「二分論」、資金に関する途上国の要求が強まる一方であることなど、この交渉プロセスに気になる点も多く残るが、しかし、各国がNationally Determined Contributionを提出し、定期的にそれを改定することが共通の義務という仕組みは既に確定している。加盟国の自主性に委ねられた制度であり、COPは交渉の場としての意義から、各国のナレッジシェアあるいはPR合戦の場へと変わるであろうことは、以前から述べている通りだ。気候変動対策をこれから進める上で重要なのは、一つには革新的技術開発であり、もう一つは社会の低炭素化を促す方向に資金の流れが変わることだ。政府間交渉と直接の関係はないテーマではあるが、COP24 でのサイドイベントでの議論などを踏まえてまとめてみたい。
-
<シリーズ>【エネルギーからみた地球温暖化問題/第32回】CO2フリー水素による産業エネルギーの化石燃料代替──2050年でのCO2排出80%
竹内 純子(NPO法人 国際環境経済研究所 理事/主席研究員) ▼概要文表示2019年1月号 -
昨年10月、東京で世界21 の国・地域・機関の代表を含め300人を超える関係者の参加を得て「水素閣僚会議」が開催された。筆者が本稿を執筆しながら参加しているCOP24でもUNIDO(国際連合工業開発機関)主催、ポーランド政府、在ウィーン日本政府代表部の共催にて水素のグローバルでの活用に向けたサイドイベントが行われた。水素利用に関する関心が高まりつつあると言えるだろう。しかしその実現に向けては多くの課題も存在する。今後の展望と、水素活用の課題を具体的に整理する。
-
<巻頭特集>【エネルギーからみた地球温暖化問題シリーズ/特別編】地球温暖化政策財団 ベニー・パイザー氏にきく 英国から考える、気候変動政策の今後
聞き手・構成:竹内 純子(NPO法人 国際環境経済研究所 理事/主席研究員) ▼概要文表示2018年12月号 -
地球温暖化問題について分析・発信を続けている英国のシンクタンク「地球温暖化政策財団」(The Global Warming Policy Foundation)のベニー・パイザー(Benny Peiser)所長が来日し、一般財団法人 キヤノングローバル戦略研究所が主催するシンポジウムに登壇した。気候変動の科学の不確実性、その不確実性を踏まえた上で気候変動政策はどうあるべきかを考えるという二部構成で進められたシンポジウムは、わが国の気候変動対策を巡る議論の中では得難い視点と示唆を与えてくれた。保守党、労働党双方の代表的な政治家、英国国教会やイングランド銀行から多様なボードメンバーを迎え、「地球温暖化問題について、できるだけ現実的な観点から、政府が採択する政策の評価をする」ことを続けている同シンクタンクの所長として活躍するパイザー氏に、EUおよびイギリスの温暖化政策の今後、IPCCの報告書に対する評価や台頭するESG投資について、そして日本へのアドバイスを伺った。
-
<シリーズ>【エネルギーからみた地球温暖化問題/第30回】拡大する「ESG投資」の課題は何か──気候変動に関する投資家エンゲージメントを巡って
竹内 純子(NPO法人 国際環境経済研究所 理事/主席研究員) ▼概要文表示2018年11月号 -
これまでも本誌において気候変動に関わる金融・投資の動きを2回にわたって紹介した。その1回目の冒頭で書いた通り、今後気候変動対策を進める上で重視されているのは、一つは革新的技術開発であり、もう一つは金融・投資のあり方であろう。投資の方針に環境対策などの非財務情報を取り込むことで社会の低炭素化を促していくことには、高い期待が寄せられている。しかし急速に拡大している分、「みんなやっている」以上に深い議論があまり聞こえてこない。そもそもESG投資の目的は「長期的リターンの最大化」であり、政策目的の投資ではないと解するのが一般的だ。目的がシンプルに「長期的リターンの最大化」であるとして、実際にESG投資はその目的に合致する成果を上げているのだろうか?「ESG投資は株主へのリターンを向上させるのか」というシンプルな問いに対して、実は全く相反する研究結果が先行する米国等において発表されている。こうした二つの見方を紹介することで、日本におけるESG投資に関する議論を深めるきっかけとしたい。
-
<シリーズ>【エネルギーからみた地球温暖化問題/第29回】「自動車新時代戦略」から考える、気候変動問題に対するわが国の貢献
竹内 純子(NPO法人 国際環境経済研究所 理事/主席研究員) ▼概要文表示2018年10月号 -
前回、パリ協定の下に各国が提出している長期戦略を概観し、気候変動に対して各国がどのように貢献しようとしているのかについて述べた。各国の長期戦略にはいくつかの共通項が見い出せたが、運輸部門からの排出削減の重要性について触れていることもその一つだ。それも当然で、化石燃料の燃焼に伴うCO2 排出量の1/4 は運輸部門が占める*1。わが国でもCO2 排出量の約18%を自動車・船舶等の運輸部門が占めており*2、これまで以上の排出削減が求められている。しかし、ドイツの長期戦略に書かれている通り、「移動は人間の根源的な欲求」であると同時に、グローバル化が進んだ現代社会においてはその必要性はより一層高まっている。運輸部門からの排出を削減するためにはどのような対策があり得るのだろうか。選択肢は多様であろうが、その一つとして政府が先日中間とりまとめを発表した「自動車新時代戦略中間整理」 *3を材料に、わが国の貢献のあり方について考える機会としたい。
-
<シリーズ>【エネルギーからみた地球温暖化問題/第28回】パリ協定「長期戦略」とは──成長戦略としての「長期戦略」を考える
竹内 純子(NPO法人 国際環境経済研究所 理事/主席研究員) ▼概要文表示2018年9月号 -
本年8月3日、安倍総理が主催する「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略策定に向けた懇談会」が開催され、パリ協定の下に提出する長期戦略(正式名称は、長期低排出発展戦略。以下、長期戦略)策定に向けた議論が開始された。これまで京都議定書やパリ協定など、気候変動に関する国際枠組みに対して、政府としての取り組みを提出することは何度か求められてきた。それらの目標年はほぼ10 数年後であり、現状の経済活動や技術から積み上げた、達成確度の高い「目標」であった。しかし、パリ協定の下に提出する長期戦略は、それらとは趣を異にする。パリ協定は、①産業革命前からの温度上昇を2℃未満(1.5℃以内への抑制も希求)に抑制すること、②今世紀後半のネット排出ゼロ、という長期目標を掲げており、これを視野に入れた長期的な「戦略」を各国が策定せねばならないのである。2016年5月に行われた伊勢志摩サミットの首脳宣言において、G7 諸国は2020年の期限に十分先立って提出することにコミットした。2018 年8 月時点においてG7 諸国のうち米・独・仏・加・英がその長期戦略を提出済みであり、日本とイタリアが未提出となっている。これまでもわが国では、環境省が中央環境審議会地球環境部会に「長期低炭素ビジョン小委員会」を、経済産業省が「長期地球温暖化対策プラットフォーム」を開催するなどして議論を続けてきたが、戦略策定には至っていない。そこで冒頭述べた通り、総理主導による懇談会が設置され、策定に向けた議論が本格化することとなったわけだが、わが国はこの長期戦略に何を書くべきなのか。パリ協定等は長期戦略に何を求めているのか、先行して提出した各国はどのような戦略を提出しているのかを分析した上で、わが国の長期戦略が踏まえるべき観点を整理したい。
-
<シリーズ>【エネルギーからみた地球温暖化問題/第27回】ドイツの電力事情(2)──CO2削減は進んだか?
竹内 純子(NPO法人 国際環境経済研究所 理事/主席研究員) ▼概要文表示2018年8月号 -
本連載の前々回において、何かと注目されるドイツのエネルギー・環境政策を取り上げるシリーズの第1回として「ドイツの電力事情── Energiewendeとは何か」を寄稿した。そこで述べた通り、Energiewendeは、将来的な化石燃料価格高騰への対処やエネルギー安全保障の確保、原子力事故の危険性排除などのリスク軽減、及び再生可能エネルギーに関わる新たな雇用の創出といった広範な目的意識の下で進められている「エネルギー転換政策」である。しかしその目的の大きな一つが温暖化対策であることは間違いがない。ドイツは電力需要の30%以上を再生可能エネルギーによって賄うなど、再生可能エネルギーの導入については順調な進展が伝えられる一方で、温室効果ガス削減についてはあまり芳しい状況ではない。本来、再生可能エネルギーの導入は手段であって目的ではなかったはずだ。なぜ本来の目的たるCO2削減がそれほど進まないのか。現状を整理し、ドイツの温暖化政策の今後を考えてみたい。
-
<シリーズ>【エネルギーからみた地球温暖化問題/第26回】次期「エネルギー基本計画」素案への評価と課題
竹内 純子(NPO法人 国際環境経済研究所 理事/主席研究員) ▼概要文表示2018年7月号 -
政府は「エネルギー基本計画」の見直しを進めている。先日素案が発表され、国民からの意見公募や政治的な承認プロセスを経て、7 月頃には確定される見通しである。「再生可能エネルギーを主力化する」という文言が使われたこと、しかし、長期エネルギー需給見通しで示した2030 年の電源構成の見直しには踏み込まなかったことなどがメディアでも取り上げられたので、ご覧になった方も多いだろう。内容としては前回の計画を踏襲したものであり、ほとんど変更点らしい変更点はない。次期計画の素案から我々は何を読み取ればよいのか。残された課題は何か。そもそも電力自由化を実施した上で、政府が将来のエネルギー・電源構成を策定する意味は何か。前回、ドイツのエネルギー政策についての連載を始めたばかりで、違うテーマに寄り道するのは恐縮であるが、タイムリーな話題として、政府が示した次期エネルギー基本計画の素案を読み解き、日本のエネルギーの将来を占いたい。
-
<シリーズ>【エネルギーからみた地球温暖化問題/第25回】ドイツの電力事情――Energiewendeとはなにか
竹内 純子(NPO法人 国際環境経済研究所 理事/主席研究員) ▼概要文表示2018年6月号 -
エネルギー政策は国民生活・社会経済に与える影響が大きく、国家戦略の中枢ともいえる。自国の資源賦存量や産業構造、気象条件や送電系統といった様々な制約条件のなかで、トレードオフの関係にある「3E(エネルギー安全保障・安定供給、経済性、環境性)」のバランスを取らねばならない。エネルギーインフラの構築には超長期の時間が必要であり、将来ビジョンを描き忍耐強く実現に向けて努力することが求められる。エネルギーの中でも特に、「インフラ中のインフラ」といわれ、他のインフラを支える存在である電力のあり方は、社会のあり方を変えるパワーを持つものであり、その政策はまさに自分たちの社会がどうありたいかという議論にほかならない。しかしその難しさのゆえか、しばしば「正解」を欧米など他国に求める議論がみられる。日本ほどエネルギー政策の議論の中で「世界の潮流」といった言葉を多用し、他国をベンチマークすることに熱心な国を、筆者は知らない。その中でも特に多く言及されるのがドイツであろう。製造業が盛んであることやGDPの大きさなど日本と類似点が多いこと、「自由化」、「再エネ」、「脱原発」という今の日本のエネルギー政策のキーワードを先取りしていることなどから、理想像として紹介されることが多い。しかし、前提条件の違いを無視して真似することはできないし、ドイツも成功ばかりではない。ドイツでは、「Energiewende」(エネルギー変革)をビジョンとしては評価しつつ、これまでのアプローチに対しては批判的な見方も多い。国民生活・社会経済に与える影響が大きく失敗が許されないエネルギー政策の議論においては、先人の好事例や失敗を見極めることが必要だ。他国を過度に評価することも、逆に、自国の制約条件に逃げ込むこともなく、真摯に学ぶことが必要だろう。これまでもドイツのEnergiewendeには注目してきたが、昨年11月、本年5月と国連気候変動交渉の会議がドイツ・ボンで開催されたため、その機会をとらえて、政府機関やシンクタンク、産業団体等へのヒアリングを行ってきた。そこで得たコメントも含めて、これから数回に分けて、ドイツの電力事情について整理したいと思う。
-
<シリーズ>【エネルギーからみた地球温暖化問題/第24回】日本の再生可能エネルギー普及を「 真面目に」考える その2──「日本版コネクト&マネージ」は機能するか
竹内 純子(NPO法人 国際環境経済研究所 理事/主席研究員) ▼概要文表示2018年5月号 -
再生可能エネルギーを主力電源として活用していくにあたり、喫緊の課題として挙げられるのが送電線への接続問題であることは前回述べた通りだ。「鑿のみと言えば槌つち」といわれるように、電気は発電したら送電できなければ意味がない。一般の消費財も生産手段と流通手段の両方を確保しなければ意味がないのと同じだ。
現在わが国は、再生可能エネルギーの電気を高値で買い取ることによって再生可能エネルギーの普及促進を図っているが、これは発電設備に経済的インセンティブを与えるだけの施策であるので、送電設備投資を促す経済的インセンティブがないばかりか、発電設備と送電設備全体で考えて社会的なコストを最小化するといった視点は含まれていない。
再生可能エネルギーの導入が容易な安価な土地には、基本的に十分な送電設備がない。人口や産業が密集していないから土地が安価なのであり、そうした地域は当然電力需要も大きくない。過度な送電線投資は当然のことながらされてこなかった。そうした地域に再生可能エネルギーを導入しようとすると、送電線への接続問題というボトルネックが発生する。
これを解決するために、「日本版コネクト&マネージ」という手法によって既存の系統を最大限活用し、発電だけでなく送電を含めた全体コストの抑制を図ることを前提に議論が進められている。昨年夏ごろから急に登場した「コネクト&マネージ」あるいは「ノンファーム型接続」という言葉に戸惑う方も多いだろう。こうした新しい言葉で消費者を煙に巻いているような気すらする。
本稿では、こうした再生可能エネルギーの系統制約に関する議論をかみ砕くとともに、そもそもどういう考え方なのか、本当にこの制度が目指すように、社会の負担を抑制しながら、自然変動電源である再生可能エネルギーの電気を使いこなしていけるのかを考えたい。
-
<シリーズ>【エネルギーからみた地球温暖化問題/第23回】「電力は足りている」のか?──厳冬に活躍した電力間融通と「ネガワット取引」
竹内 純子(NPO法人 国際環境経済研究所 理事/主席研究員) ▼概要文表示2018年4月号 -
本年1 月下旬から2 月上旬にかけて、日本は強烈な寒波に襲われた。北陸地方を中心に影響を受けられた方には心からのお見舞いを申し上げたい。しかし豪雪の被害や車の立ち往生などに報道が集中した一方で、その時期関東地方の電力供給は大きな危機に瀕していたことはほとんど認識されていない。2 月2 日には前日時点予備力見込みは、他社からの融通を受けられないとすると0. 6%まで低下するとされ、肝を冷やした関係者も多かっただろう。
今回の需給ひっ迫の際はなぜ発生し、どうやって乗り切ることができたのだろうか。電力の安定供給確保は国民生活に欠かすことができないものであり、この冬の経験から今後への教訓を読み取ることが重要だ。これから関係機関の詳細な分析が行われることになろうが、本稿では、「電力は足りている」のかを検証する意味も含めて今の時点でできる整理を行っておきたい。
-
<シリーズ>【エネルギーからみた地球温暖化問題/第22回】日本の再生可能エネルギー普及を「真面目に」考える──中長期的な再エネ大量導入に向け、いま何が必要か
竹内 純子(NPO法人 国際環境経済研究所 理事/主席研究員) ▼概要文表示2018年3月号 -
2012 年の固定価格買取制度(以下、FIT)導入以降、再生可能エネルギー(以下、再エネ)の普及が急速に進んでいる。これを中長期的な大量導入につなげ、再エネを主力電源としていくためには何が必要であろうか。喫緊の対処として、再エネに関わるコスト全体を抑制することを求めたい。再エネに関わるコストとしては、まず導入支援のための直接的コストがある。FITの下、「再エネ発電賦課金」は今や一般家庭の電気料金の1 割以上にもなり、産業活動にも大きな負担となっている。もう一つ、再エネの導入量が増えるにつれて増大するのがネットワークコストだ。「再生可能エネルギーをうまく使いこなすためのコスト」といえばわかりやすいだろうか。送電網の拡充や調整電源の維持など、自然変動電源である太陽光・風力を大量に受け入れつつネットワークの安定性を確保するためのコストが必要になる。
こうした再エネにかかるトータルの国民負担をコントロールしていくことが、持続的な再エネ導入には不可欠である。
-
<巻頭特集>エネルギーからみた地球温暖化問題シリーズ/特別編 英国再生可能エネルギー財団 ジョン・コンスタブル氏にきく イギリスのエネルギー政策と再生可能エネルギー問題
聞き手・構成:竹内 純子(NPO法人 国際環境経済研究所 理事/主席研究員) ▼概要文表示2018年2月号 -
2004 年に英国で「Renewable Energy Foundation(以下、REF)」を設立し、精力的に再生可能エネルギーに関するデータ提供や政策提言を行っているジョン・コンスタブル氏が昨年末、キヤノングローバル戦略研究所のセミナーに登壇するため来日した。筆者も同セミナーにディスカッサントとして参加することとなり、それを機にインタビューをさせていただいた。
REF設立のきっかけは、ご自身のお母様の家の近くで風力発電の建設計画が持ち上がったことにあったという。それほど風が強いところでもなく、風力発電に適しているとは思い難いのに、なぜ建設計画が持ち上がったのかと疑問に思い調べていくと、過剰な補助制度が原因であると気づいたという。そんな政策のツケを背負うのは子供たちであると強い危機感を抱くに至り、企業からの寄付は受けず民間の寄付だけで活動するREFを立ち上げた。今回、再生可能エネルギー普及における政府の役割、英国の温暖化政策の見通し、日本へのアドバイスについてお話を伺った。
-
<シリーズ>【エネルギーからみた地球温暖化問題/第20回】日本の原子力に未来はあるか?
竹内 純子(NPO法人 国際環境経済研究所 理事/主席研究員) ▼概要文表示2018年1月号 -
わが国が原子力基本法を制定し、原子力技術の利用を正式に決定したのは1955 年。わずか終戦から10 年後のことであった。その時の判断が、メリットとデメリットを比較衡量する国民的議論に基づくものであったのか否かは、筆者には語り得ない。
しかし東京電力福島原子力発電所事故を経験し原子力政策が見直されている今、将来に向けては我々国民が判断する権利があり、また義務があるといえるだろう。もちろん、世論に判断を丸投げすることは、政治あるいは関係者の責任放棄でしかない。原子力発電を利用することによるメリットとデメリット、青森県との関係や日米原子力協定などこれまでの歴史的経緯による制約条件等を踏まえる必要があり、十分な情報提供がなされることが前提だ。政府は2030 年の電源構成において、22~20%を原子力で賄うとするが、2030 年時点でそれだけの原子力発電所を維持できるのか、維持できなかった場合温暖化の国際目標の達成など長期エネルギー需給見通しの前提をどうするのか、さらにその先に向けてはどうするのかについて、具体的な方針は示されていない。原子力技術の維持や人材育成の観点から考えれば早急に方向性を示すことが求められる。日本のエネルギー政策を考える上では、原子力事業をどうするかで取り得る選択肢が全く異なってくるのであり、議論されるべき論点について整理したいと思う。
-
<シリーズ>【エネルギーからみた地球温暖化問題/第19回】原発の電気は安いのか?(後編)
竹内 純子(NPO法人 国際環境経済研究所 理事/主席研究員) ▼概要文表示2017年12月号 -
前回は、仮想の原子力発電所新設プロジェクトの資金計画を様々なケースに応じて確認することで、原子力発電に安価な電力を供給させるのであれば、相応の条件整備が必要であることについて整理した。
制度設計次第でコストが変わることは原子力発電に限ったことではなく、OECD/NEA・IEAの報告書の言葉を借りれば、“ There is no single technology that can be said to be the cheapest under all circumstances.”(どんな状況下においても最も安いといえるような単独の技術はない)のであるが、資本集約率が高く莫大な資金調達を必要とする原子力発電においては政策的支援の必要性が特に顕著である。そのため、電力自由化を実施して発電事業に対する投資回収の可能性が低下してしまった状況においてなお原子力発電を維持しようとする米国や英国においては、リスク平準化や一部のリスクを遮断する政策が講じられている。むしろ米国や英国では、自由化と食い合わせの悪い原子力事業をどう維持するかは、システム改革の初期段階で議論されるべき難題であると認識されていたのである。
日本ではこれまでなぜ54 基もの商業用原子力発電所建設が可能だったのか、及び、自由化した米国、英国で採られている原子力政策を整理し、今後のわが国への今後の示唆を読み解いてみたい。
-
<シリーズ>【エネルギーからみた地球温暖化問題/第18回】原発の電気は安いのか?(中編)
竹内 純子(NPO法人 国際環境経済研究所 理事/主席研究員) ▼概要文表示2017年11月号 -
保すること、資金調達コストを低減し得るよう信用力の補完策を講じるなど、条件を整える必要があるのだ。
制度設計次第でコストが変わることは原子力発電に限ったことではないが、資本集約率の高い原子力発電においては特に顕著となる。そのため、電力自由化を実施してなお原子力発電を維持しようとする米国や英国においては、政策的支援策が講じられているが、わが国においては、次期エネルギー基本計画でも原子力をどう扱うか見通しが立っていない。
震災後に策定された新規制基準に適合した発電所( 再稼働)もようやく全国で5 基という現状において、わが国の原子力技術利用の将来を議論するのは時期尚早であるとの批判もあるだろう。しかし、原子力という技術のメリットを概念的に述べるのではなく、数字で議論しなければ国民も判断はできない。社会がある技術の利用をするか否かは、その技術の利用に伴って得られるメリットとデメリット(リスク)の比較衡量によるのであり、リスクをどこまで減じられるか、逆に利用しないことで生じるリスクは他で代替できないのかを徹底的に検討する必要がある。同時にどうすればその技術利用に伴って国民が享受するメリットを最大化しうるのかも検討せねばならない。原子力発電も含めて各電源のコストについては、これまでにもいくつかの試算が示されていたが、資金調達コストや稼働率などの変数がどの程度原子力のコストに影響を与えるのかについて定量的に十分語られて来たとはいいがたい。もちろん原子力については、バックエンド事業のようにコスト見通しが困難な事業もある。しかしできる限り定量的な評価を行った上で、メリットとデメリット(リスク)を比較考量し、今後もわが国が原子力技術を利用するのかどうか判断すべきであろう。
原子力過酷事故のテールリスクや原子力規制の厳格化などによって、かつてに比べ事業リスクが高まっているうえ、そもそも自由化されれば、電力会社の財務健全性が厳格に評価され、資金調達コストに反映されることになる。このままであれば日本で民間事業者による原子力の新設・リプレースが起こることは期待できないだろう。既存の原子力発電所の運転期間終了に伴って、着々と脱原発が進むに任せておけばよいのであればそれでよい。しかしそうではない場合に備えた頭の体操をしておきたいと思う。
-
<シリーズ>【エネルギーからみた地球温暖化問題/第17回】原発の電気は安いのか?(前編)
竹内 純子(NPO法人 国際環境経済研究所 理事/主席研究員) ▼概要文表示2017年10月号 -
新たなエネルギー基本計画策定に向けて、わが国の今後のエネルギー政策のあり方が改めて議論されている。2014 年に策定された第4 次エネルギー基本計画では、エネルギー政策の基本は3E+Sにあることを踏まえて、徹底した省エネと再エネの導入加速、福島の復興を前提とした原子力事業の再構築と火力発電の高効率化などの方針が示されていた。次期計画において基本的な考え方に大きな変更があるとは考えられず、世間の関心は専ら、原子力の新設あるいは建替えに関して政府の方針が示されるかどうかに集中しているようにみえる。
前回基本計画では、新規制基準に合格した原子力発電所については再稼働を進めるというスタンスが明示された。しかし、原子力事業の長期的なビジョンが示されることはなかった。原子力発電所の運転期間が40 年、特別点検を受けて延長したとしても60 年に制限されていることを考えれば、新設あるいはリプレース( 建替え)がなければ、わが国から原子力発電事業がなくなることは明らかであり、結論に関わらず、この議論が避けられないことは確かだ。
とはいえ、本来再稼働を進める前にやらねばならないことも山積している。前回基本計画で掲げた通り、福島の再生・復興に向けた取組みを着実に進めること、安全基準の遵守だけでなく発電所の安全性に一義的な責任を負う事業者が自主的かつ不断の取組みを続ける仕組みを構築すること、それでも万一事故が起きたときに備え原子力損害賠償法や原子力防災を充実させること等、多くがまだ取組みの途上だ。廃棄物の処理を含む核燃料サイクル政策の動向も不透明であり、この状態で新設・リプレースを議論することは非現実的であるとして批判も強い。しかし、今世紀半ばには温室効果ガスの8 割減を目指すという政府方針も踏まえれば、原子力発電所の必要性を否定できるものでもなく、新設・リプレースに要する時間を考えれば、今から議論を始めても決して早くはない。
しかし、日本の将来のエネルギー供給においてどれだけ原子力の貢献を期待するかは、その「お値段」次第でもある。もちろん原子力の価値は、発電時にCO2 を排出しないという環境性、エネルギー自給率に貢献する点にも見出すことはできるが、そうした公共的価値よりも消費者にとって目に見えやすいのが経済性である。しかし原子力発電所の電気は本当に「安い」のだろうか? 東京電力福島原子力発電所事故によって原子力災害のコストが顕在化し、消費者は原子力の安全神話とともに経済性の神話も崩壊したと受け止めている。
改めて、「原発の電気は安いのか」について考えてみたい。
-
<シリーズ>【エネルギーからみた地球温暖化問題/第16回】天然ガスにもダイベストメントの波が来るのか?──TCFD最終報告書を踏まえて考える気候関連財務ディスクロージャーの展望と課題
竹内 純子(NPO法人 国際環境経済研究所 理事/主席研究員) ▼概要文表示2017年9月号 -
トランプ大統領は正式にパリ協定を離脱する旨を国連に通告したが、投資家がESG投資への関心を高め、エンゲージメント、ダイベストメントという形で低炭素化社会への移行を促す動きに陰りはみえない。
そんな中で最近、天然ガスの座礁資産化*1を警告する論が台頭してきている。環境性が高いとされる天然ガスではあるが、それは石炭や石油との比較においての話でしかない。パリ協定が掲げた長期目標達成のためには、天然ガス関連施設も遠からずお蔵入りさせねばならない(発電設備については、バイオガスを代替燃料として利用することも言及されている)というのが「天然ガス座礁資産化論」の指摘だ。
燃焼時にCO2 を排出することが理由で石炭関連産業からのダイベストメントを主張するのであれば、天然ガスと石炭はまさに五十歩百歩。これまで石炭だけを悪者としてきた議論がバランスを欠いていたのであり、こうした論が出てくることは当然の流れであろう。参照シナリオによって座礁資産の定義は変わるのであり、これは企業が「気候変動関連リスク」の情報開示をするにあたっての課題の一つともなっている。
そして石炭も天然ガスも、IEA(国際エネルギー機関)の予測等を参照すれば、今後も途上国の経済発展を支えるエネルギー源であると考えられている。それらが近い将来座礁資産と化すとの論は果たして現実的なのであろうか。可能性は無視すべきではないが、確率の問題を無視した議論になっているという懸念は指摘せざるを得ない。
これまでこの連載でも繰り返し指摘してきた通り、気候変動による企業の財務・金融リスクの情報開示は、いわば理念先行、議論が未成熟であることは確かだ。しかし、そうした情報開示を企業に求める動きがこれまで以上に活発になっていることは指摘しておきたい。具体的には、オイルメジャーなど複数の会社が今年の株主総会において、2℃シナリオを前提とした各社の事業見通し、長期ポートフォリオの評価を行うことを求められ、決議されているのだ。今後彼らは、2℃シナリオを前提に個社の事業見通しや長期ポートフォリオを分析し、財務・金融リスク情報を開示することになるわけだが、2℃シナリオというグローバルでマクロなシナリオと企業の活動を整合的に分析しうるのかが注目される。
企業の気候関連財務ディスクロージャーを求める動きとその課題、7 月15 日に公表された「気候関連財務ディスクロージャータスクフォース( Task Force on Climate-related Financial Disclosures,TCFD)の最終報告書等を整理し、企業活動に大きな影響を与えうるこの議論の動向を占う。
-
<シリーズ>【エネルギーからみた地球温暖化問題/第15回】トランプ政権のパリ協定離脱を整理する――その真意と影響は?
竹内 純子(NPO法人 国際環境経済研究所 理事/主席研究員) ▼概要文表示2017年7月号 -
米国のトランプ大統領は6月1日午後3 時(日本時間2日午前4時)、ホワイトハウスのローズガーデンで演説し「パリ協定」からの脱退を宣言した。政権内部でも残留派と離脱派が鋭く対立し、リーク合戦の様相を呈したメディアの報道も直前まで続いた。離脱したこと自体はトランプ大統領が選挙キャンペーン中の公約として掲げていたことを実行したものであり、大きな驚きはない。オバマ政権が掲げた削減目標を履行しないことは、本年3月に国内対策を見直す大統領令に署名していることからも明らかであったし、COP21で表明された米国の「緑の気候基金(GCF)」に対する30億米ドルの拠出の内、既にオバマ政権下で2回に分けて拠出された10 億ドルを除く20億ドルの拠出は全く期待できないことも明らかであった。
しかし、演説の中で「再交渉」「再加入」という含みを残した真意や、今後具体的にどのような手続きで離脱するのかについては全くクリアになっておらず、離脱の影響がどこまで及ぶのかは定かではない。詳細は今後政権内での議論の進展を待つしかないが、今の時点での整理を試みる。
-
<シリーズ>【エネルギーからみた地球温暖化問題/第14回】カーボンバジェットあと1,000Gtは本当か──ハイブリッドアプローチを採るパリ協定を維持する観点から考える
竹内 純子(NPO法人 国際環境経済研究所 理事/主席研究員) ▼概要文表示2017年6月号 -
パリ協定が採択された瞬間、歓喜の渦に包まれたCOP21 会場にあって、筆者はどうしてもそれほどに楽観的にはなれなかった。
パリ協定はいわゆる2℃目標という長期目標を共有したうえで、各国の貢献については各国の自主的な設定を認める。「ハイブリッドアプローチ」とも評されるこの仕組みは、これからのルール設計の過程でトップダウンアプローチの色合いが濃くなれば各国の離脱(協定からの明示的な離脱のみならず、達成に向けた努力の静かなる放棄も含む)を招くであろうし、自主性を過剰に認め公平かつ実効性ある対策努力が引き出せなくなれば、温暖化対策が進まない。
そもそも協定の条文に書き込まれた2℃目標は政治的に生まれ、徐々に気候変動交渉の世界の「常識」として定着したものである。さらに、その2℃目標を達成するためには、気候感度の前提の置き方次第で様々な道筋があり得るが、わかりやすい単一な数字が「守るべき予算」として独り歩きしている。本来は最新の科学的知見に基づいて国際的枠組みが議論されるべきであるが、一旦独り歩きをし始めた数字について科学的根拠を問う議論は、「厳しめに考えておいたほうが良い」というナイーブな声の前にかき消されがちである。
しかし我々の目標に近づくパスは多様に存在することを前提に議論しなければ、パリ協定の仕組みそのものを瓦解させてしまいかねない。温暖化対策至上主義に陥ることは、温暖化対策を進める上で決して得策ではない。
パリ協定の構造と2℃目標、それを達成するために必要とされるカーボンバジェット残り1,000Gtを整理したうえで、現在のUNFCCCでの議論を概観する。
-
<シリーズ>【エネルギーからみた地球温暖化問題/第13回】再エネ賦課金の抑制は可能か?――改正FIT法と非化石価値市場の創設
竹内 純子(NPO法人 国際環境経済研究所 理事/主席研究員) ▼概要文表示2017年5月号 -
再生可能エネルギー賦課金の増大が止まらない。先日公表された平成29 年度の賦課金も、前年度比約2 割の上昇である。1 か月の電力使用量が300kWhとした場合の負担額は年額9,504 円にもなる。より深刻なのは産業への影響だ。企業の電気料金はなかなかオープンにされることはないが、莫大な賦課金に驚き、自身の勤める会社の工場における電気料金を教えて下さった方がいた。その方によれば、本年1 月分の電気料金約5,600 万円、そのうち実に約1,600 万円がFIT賦課金であったという。
わが国の再エネ賦課金はなぜここまで膨れ上がってしまったのであろうか。こうなることは他国の経験から明らかであったし、採るべき対策もわかっていた。しかしそれを制度設計に活かすことができなかったのである。筆者が危惧するのは、特にこの制度設計をここまでゆがめたことに対する政治の反省が全くないことだ。これでは過ちを修正することはできない。
FIT法は確かに改正され、非化石価値市場の創設による抑制なども検討されている。しかし、それが十分な抑制策になり得るとは筆者には考えづらい。2030 年のエネルギーミックスが達成された場合、2030 年までの累積賦課金総額は44 兆円になるとの試算も出されている。エネルギーコスト抑制に向けた政府の本気度を問いたい。
-
<シリーズ>【エネルギーからみた地球温暖化問題/第12回】経済成長とCO2排出量の デカップリングを考える── 米国オバマ政権の「成果」を問う
竹内 純子(NPO法人 国際環境経済研究所 理事/主席研究員) ▼概要文表示2017年4月号 -
近年一部の先進国では、経済成長は維持しながらも、CO2 排出量を削減する、いわゆる「デカップリング」を達成しているとする主張をしばしばみかける。米国のオバマ前大統領もScience誌への投稿の中で、自身の政権の成果としてデカップリングに成功した実績を強調し、それをもたらした理由としてシェール革命による石炭から天然ガスへの燃種転換と再生可能エネルギーの普及を挙げている。より強調されているのは後者の方で、再生可能エネルギーは政府の支援策もあって既に価格競争力を持つようになりつつあること、民間企業の自主的な動きや各州政府の取り組みもあって、この流れは止め
ようがないものであるとして、トランプ新政権に釘を刺している。
しかしデカップリングをもたらした要因を分析すると、まだ「再生可能エネルギーの導入がグリーン成長の原動力」と断じるには早いようだ。グリーン成長を実現していくためには、経済成長とCO2 の相関関係を「過去のもの」と切り捨てるのではなく、現実を踏まえた上で何をすべきかを真摯に考える必要がある。現在デカップリングと言われる現象をもたらしている要因についての公益財団法人 地球環境産業技術研究機構(RITE)の分析を紹介し、デカップリングについて考える機会としたい。
-
<シリーズ>【エネルギーからみた地球温暖化問題/第11回】 続・気候変動を動かす金融・投資の動き――TCFDの提言案を読む
竹内 純子(NPO法人 国際環境経済研究所 理事/主席研究員) ▼概要文表示2017年3月号 -
昨年の本誌8 月号に寄稿した「気候変動を動かす金融・投資の動き」において、気候変動対策を進める重要な動きの一つとして、金融・投資のあり方の変化について述べた。経済発展と温室効果ガス排出量のデカップリングを可能にするには革新的技術と社会全体の変革が必要であり、その変化を促す原動力として、金融市場の投資判断基準に気候変動に関する価値観を取り込む動きが活発になっている。というよりも、リーマンショックを経験した金融市場が、気候変動が引き金となって金融危機につながる可能性を懸念し、情報開示を求めていると表現したほうが正しいかもしれない。その急先鋒の動きが、金融安定化理事会(FSB)が設置した民間有識者によるタスクフォース(TCFD)であろう。メンバーが公表されたのが2016 年1 月、3 月末にはフェーズⅠ報告書を公表、12 月14 日には「気候関連財務情報開示タスクフォースによる提言(以下、フェーズⅡ報告書)」を公表するという早さである。2017 年2 月12 日までパブリックコメントを受け付けたあと、3 月にFSBに報告、6 月には最終報告と公表を行い、7 月にはG20 サミットに報告する予定だ。
「気候変動を動かす金融・投資の動き」において、TCFDから金融安定化理事会(FSB)への答申の内容によっては今後企業の情報開示のあり方に大きな影響を与える可能性があり、これが健全な企業活動と市場の選択を促す内容となるよう注視していく必要があると指摘したが、今回公表されたフェーズⅡ報告書は何を述べているのであろうか。概要を整理するとともに、筆者が感じる疑問、そして今後これがどのように使われるかの見通しを考える。
-
<シリーズ>【エネルギーからみた地球温暖化問題/第10回】2050年のエネルギーを考える思考実験─―宮古島「すまエコプロジェクト」に見る電化の流れ
竹内 純子(NPO法人 国際環境経済研究所 理事/主席研究員) ▼概要文表示2017年2月号 -
2050 年。今から33 年後のわが国はどのような社会になっているのであろうか。どの程度のエネルギーを必要とし、それをどうやって賄っているのか。世界のエネルギー・環境政策にどのように貢献しているのか。エネルギーに関する技術開発やインフラの構築に必要な時間軸を考えれば、2050 年は決して遠い未来ではない。しかし、今から33 年前、携帯電話はもちろんスマートフォンがこれほどに普及することなど誰も予測していなかったように、これから33 年後には私たちの社会を激変させる技術が生み出されているかもしれない。
未来を見通すことは不可能ではあるが、より良い社会を後世に遺すためには、どのような変化要因に配慮しながら制度設計を考えていけばよいのか。
日本のエネルギーを巡る環境を激変させる要因は様々あるが、「五つのD 」、すなわち、人口減少(Depopulation)、分散化(Decentralization)、自由化(Deregulation)、脱炭素化(De-Carbonization)、そしてデジタル化(Digitalization)が挙げられるだろう。ちなみに欧州電気事業関係者の間では、3D+S、すなわち「脱炭素化」( Decarbonization )、「デジタル化」( Digitalization )、「分散化」(Decentralization)と「部門結合」(Sector Coupling)がメガトレンドといわれている。
複雑に絡み合うこれらの変化要因に対しては、技術の進展と社会の構造・意識改革の両面から柔軟に対処することが必要であり、すべてを一気に解決するような魔法の杖は存在しない。しかし、待ったなしの課題に先駆的に取り組もうとする動きは各地でみられる。沖縄県宮古島市で行われているプロジェクトを例に、2050 年の日本のエネルギーに関する思考実験をしてみたい。
-
<シリーズ>【エネルギーからみた地球温暖化問題/第9回】米国大統領選挙に揺れた COP22を振り返る
竹内 純子(NPO法人 国際環境経済研究所 理事/主席研究員) ▼概要文表示2016年12月号 -
米国大統領選挙の結果、事前の大方の予想を覆し、共和党トランプ候補が圧勝した。また、同時に行われた議会選挙の結果、共和党が上下両院ともに過半数を占めることとなった。エネルギー・環境政策については選挙期間中もメインイシューにはなっておらず、今後の政策を占うに十分な手掛かりがあるとは言い難いが、新政権が気候変動対策に積極的ではないことだけは明らかだ。昨年のパリ協定採択に大きな役割を果たした米国の方向転換が確実視されるとあって、協定発効に湧いていたCOP22 の会場も冷や水を浴びせかけられた格好だ。交渉関係者は冷静さを保っていた印象ではあるが、NGO 関係者などからは多くの不安や批判の声が聞かれた。
トランプ氏は強いアメリカを取り戻すことを公約として掲げ、国内の石炭・石油産業を保護し、エネルギー自給率を高めていくとしている。EUもエネルギー政策のプライオリティをエネルギー安全保障に置き、米国とのエネルギー価格格差に対しても神経をとがらせている。米国も欧州も、気候変動という地球規模かつ科学的な不確実性の高い課題に取り組むよりも、目の前に確実に存在する国内経済や外交についての課題に対処し、足元を固めることを望む大衆の声が勝ってきているのだろう。翻って考えるに、エネルギー自給率わずか6%の日本で、そのことへの問題意識があまり聞かれないことには、強い危機感を抱かざるを得ない。
トランプ氏がどのような政権運営を行うのか、まずは冷静にその舵取りを注視すべきであり、今後の米国のエネルギー・環境政策がどう動くかを語るには時期尚早であるが、選挙期間中の発言や選挙後の動きから、今後想定される米国のエネルギー・環境政策を占うとともに、わが国のとるべき影響などを俯瞰したい。
-
<シリーズ>【エネルギーからみた地球温暖化問題/第8回】パリ協定発効を踏まえて考える日本の貢献
竹内 純子(NPO法人 国際環境経済研究所 理事/主席研究員) ▼概要文表示2016年11月号 -
昨年のCOP21 で採択されたパリ協定は、各国の批准手続きが順調に進み、COP22 の開催を前に発効することが確定的となった。COP22 で「第1 回パリ協定締約国会議( CMA1)」が開催されることになるため、日本も早期に国会承認を得るべく議論を急いでいる(本稿執筆時において)。今後わが国は2030 年26%削減という目標達成に向けた議論を加速すると同時に、途上国での削減および適応策に適切に貢献していくことが求められる。パリ協定に提出した自国の削減目標を達成に向けて努力することはもちろん、隔年報告等によって途上国への貢献についても明らかにしていくことが義務付けられているからだ。
COP21 あるいはその後の特別作業部会での議論をみても、途上国が適応策への支援に対して特
に強い関心を抱いている中、改めて適応策に対する貢献のあり方を考えることが必要であるし、わが国の企業が持つ技術で、途上国の適応策に有効なものも多い。相手国のニーズを的確に把握し、多様な技術を組み合わせることなどで気候変動適応策としてストーリーを描き「見える化」していくことができれば、途上国政府とのB to Gのビジネスが拡大することも期待しうるだろう。インドネシアの適応計画やそこで展開する日本企業の貢献の事例を概観し、これまで削減策への貢献と比較して議論が十分ではなかった、適応策への貢献について考える。
-
<シリーズ>【エネルギーからみた地球温暖化問題/第7回】 わが国の省エネはどこまで期待できるか
竹内 純子(NPO法人 国際環境経済研究所 理事/主席研究員) ▼概要文表示2016年10月号 -
昨年示されたわが国の長期エネルギー需給見通し( 以下、エネルギーミックス)は、5,030 万kLという大幅な省エネの進展を前提にしている。2030年度にかけて35%という大幅なエネルギー効率の改善が期待されているわけだが、これは1970年代からの20 年間にわが国が達成した効率改善と同程度である。しかしわが国のエネルギー需要の価格弾性値はいずれの分野においてもオイルショック当時より大幅に縮小しており、価格による省エネ促進効果は薄れている状況にある。こうした状況を踏まえて、今後エネルギーミックスで期待されている省エネを実現していくためには何が必要かを考える。
-
<シリーズ>【エネルギーからみた地球温暖化問題/第6回】 電力の低炭素化をどう図るか――自主的枠組みへの期待と課題
竹内 純子(NPO法人 国際環境経済研究所 理事/主席研究員) ▼概要文表示2016年9月号 -
電力の低炭素化は、わが国がパリ協定の下に掲げた目標「2030 年には2013 年比マイナス26%」達成の重要なカギである。電力の排出係数はすべての需要部門の排出量に影響を与えるため、電力事業者は「電気事業低炭素社会協議会」を設立して排出係数目標を共有し、その実現に向けて自主的に取り組んでいくこととしている。政府は「長期エネルギー需給見通し」( 以下、エネルギーミックス)の達成をより確実にするため、発電段階では「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」( 以下、省エネ法)を、小売り段階では「供給構造高度化法」( 以下、高度化法)を適用し、電力事業者の自主的取り組みを支えていく。しかし現状の実績をみれば、省エネ法及び高度化法で求められる基準を達成することは相当にハードルが高い。電力の低炭素化に向けた取り組みへの期待と政策の課題を整理したい。
-
<シリーズ>【エネルギーからみた地球温暖化問題/第5回】 気候変動を動かす金融・投資の動き
竹内 純子(NPO法人 国際環境経済研究所 理事/主席研究員) ▼概要文表示2016年8月号 -
「持続可能な開発のための2030アジェンダ」や「パリ協定」が採択された翌年、実施を図る最初の年に日本が議長国となり、7年ぶりとなるG7環境大臣会合を5月15、16日に富山市において開催した。今回の会合では、我々が直面する様々な課題の解決に向けて議論し、G7各国の強い意志を示すとともに、他のセクターの政策との統合の必要性、環境保全の取組が経済的にも評価される仕組みの必要性を強調することで一致した。ここでは、会合の成果と今後の政策の方向性を述べる。
-
<シリーズ>【エネルギーからみた地球温暖化問題/第4回】 再エネ普及政策はどうあるべきか――FIT法見直しの経緯と概要
竹内 純子(NPO法人 国際環境経済研究所 理事/主席研究員) ▼概要文表示2016年7月号 -
第190 回通常国会にて「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(通称:FIT法)等の一部を改正する法律」が成立、6 月3 日に公布された。少なくとも3 年ごとに様々な状況変化を踏まえ「必要な措置を講ずること」は規定されていたことではあるが、再エネによる発電電力量をわずか約2%押し上げるために費やされた莫大なコスト、そして、大量の未稼働案件発生という事前の想定を超える事態に直面し、修正を余儀なくされたことは事実であろう。制度が導入された2012 年7 月から今日まで、どのような効果をあげ、副作用がもたらされたのか。その間に進んだ電力システム改革との整合性において考えるべきは何か。日本の再エネ普及政策について整理する。
-
<シリーズ>【エネルギーからみた地球温暖化問題/第3回】 排出量取引の"理想と現実"──EU-ETSの評価
竹内 純子(NPO法人 国際環境経済研究所 理事/主席研究員) ▼概要文表示2016年6月号 -
排出量取引はCO2 排出という外部不経済を内部化するための手段の一つである。炭素排出に対する価格付け(カーボンプライシング)には複数の手法があるが、炭素税や再エネ導入促進がどれだけの排出削減量を確保できるか明確ではないのに対して、排出量を一定に制限できる排出量取引は環境経済学者や温暖化対策に熱心な方の支持が高い。しかしIPCC第5 次評価報告書においてEU-ETS(EU域内排出量取引制度)が「環境的な効果は限定的だった」と評価されるなど、その理想と現実にギャップがあることも明らかになってきている。 本稿では、カーボンプライシングの潮流を概観したあと、導入から既に10 年以上の経験を積んできたEU-ETSを例に同制度の課題を整理する。
-
<シリーズ>【エネルギーからみた地球温暖化問題/第1回】 オバマ政権クリーンパワープランはどう動くか──パリ協定後の石炭火力発電
竹内 純子 NPO法人 国際環境経済研究所 理事/主席研究員 ▼概要文表示2016年4月号 -
「エネルギー」と「環境問題」の現場を歩き、地球温暖化を論考するシリーズ。