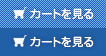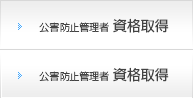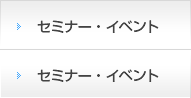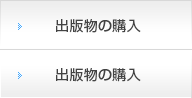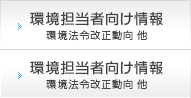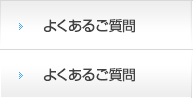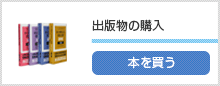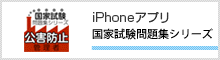- HOME
- 環境担当者向け情報 (JEMAI CLUB)
- 環境関連法改正情報
- キーワードサーチ 検索結果
キーワードサーチ 検索結果
カテゴリアーカイブ
キーワード「事業者」が付けられているもの
| 省エネ法(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律)関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 | 工場等における電気の需要の最適化に資する措置に関する事業者の指針(平成25年経済産業省告示第271号) |
| 改正条項 |
2-1(1)イ
|
| 公布番号と名称 | 経済産業省告示第147号 工場等における電気の需要の最適化に資する措置に関する事業者の指針の一部を改正する告示 |
| 公布日 | 令和5年12月8日 |
| 施行/適用日 | 令和5年12月15日 |
| 制定/改正の概要 | 電気加熱設備、電動力応用設備等の産業用機械器具について、電気需要最適化時間帯を踏まえ、電気を消費する機械器具の稼働時間の変更を検討することが盛り込まれた。 |
| キーワード | |
| 省エネ法(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律)関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 | 一般消費者に対するエネルギーの供給の事業を行う者が講ずべき措置に関する指針(平成18年経済産業省告示第235号) |
| 改正条項 |
第1、4、5、6項
|
| 公布番号と名称 | 経済産業省告示第86号 一般消費者に対するエネルギーの供給の事業を行う者が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する告示 |
| 公布日 | 令和5年6月23日 |
| 施行/適用日 | 令和5年6月23日 |
| 制定/改正の概要 | 標記指針第1及び6項(改正前4項)が改正され、第4、5項が新設された。 |
| キーワード | |
| 省エネ法(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律)関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 | 事業者が自主的に行う技術の提供、助言、事業の連携等による他の者のエネルギーの使用の合理化の促進に寄与する取組に係る報告の様式を定めた件(令和4年経済産業省告示第83号) |
| 改正条項 |
様式(共同省エネルギー事業の報告)
|
| 公布番号と名称 | 経済産業省告示第87号 令和4年経済産業省告示第83号(事業者が自主的に行う技術の提供、助言、事業の連携等による他の者のエネルギーの使用の合理化の促進に寄与する取組に係る報告の様式を定めた件)の一部を改正する告示 |
| 公布日 | 令和5年6月23日 |
| 施行/適用日 | 令和5年6月23日 |
| 制定/改正の概要 | 標記第1表の備考その他が改正された。 |
| キーワード | |
| 省エネ法(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律)関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 | 工場等における非化石エネルギーへの転換に関する事業者の判断の基準(令和5年経済産業省告示第28号) |
| 改正条項 |
全部
|
| 公布番号と名称 | 経済産業省告示第28号 工場等における非化石エネルギーへの転換に関する事業者の判断の基準 |
| 公布日 | 令和5年3月31日 |
| 施行/適用日 | 令和5年4月1日 |
| 制定/改正の概要 | 工場等における非化石エネルギーへの転換に関する事業者の判断の基準として、工場又は事務所その他の事業場(以下「工場等」という。)においてエネルギーを使用して事業を行う者(以下「事業者」という。)は、非化石エネルギーの供給の状況、当該事業者の工場等における電気の需要の最適化に資する措置に関する事業者の指針に従って講じた措置の状況その他の事情に応じて、技術的かつ経済的に可能な範囲内で、その設置している全ての工場等を俯瞰して行う非化石エネルギーへの転換の取組として、を行うこと。全ての事業者が取り組むべき事項と工場等において取り組むべき事項が定められた。 |
| キーワード | |
| 労働安全衛生法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 | 石綿障害予防規則 |
| 改正条項 |
第3条第4、7、9、11、12項
|
| 公布番号と名称 | 厚生労働省令第2号 石綿障害予防規則の一部を改正する省令 |
| 公布日 | 令和5年1月11日 |
| 施行日 | 令和8年1月1日 |
| 制定/改正の概要 | 石綿等が使用されているおそれが高いものとして厚生労働大臣が定める工作物以外の工作物の解体等の作業に係る事前調査について、記録に関する規程が改正された。 |
| キーワード | |
| 法名 |
省エネルギー法(エネルギーの使用の合理化等に関する法律)
|
|---|---|
| 改正条項 | 別表第5 |
| 改正年月日 | 令和4年3月31日 令和4年3月31日 経済産業省告示第81号 |
| 施行日 | 令和4年4月1日 |
| キーワード | |
| 改正の概要 | 省エネ法定期報告の令和元年度実績において、一部の業種・分野では省エネ取組の進展等により、ベンチマーク目標達成事業者が50%以上となり、目標値が「事業者が目指すべき高い水準」とみなせない状況となったことから、ソーダ業、国家公務の目標値が見直された。また、エネルギー使用量の多い業種(データセンター、圧縮がす・液化ガス製造業)が追加された。 |
| 法名 |
容器包装リサイクル法
|
|---|---|
| 改正条項 | 法第7条の4、小売業に属する事業を行う者の容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
| 改正年月日 | 令和元年12月27日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第4号 |
| 施行日 | 令和2年7月1日 |
| キーワード | |
| 改正の概要 | 指定容器包装利用事業者は、プラスチック製買物袋の有料化に取り組む必要がある。ただし、プラスチックの厚さ50μm以上の買物袋、海洋生分解性プラスチック配合率100%の買物袋、バイオマス配合率25%以上の買物袋等は有料化の対象からは除く。 |
| 法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
|
|---|---|
| 改正条項 | 改正法第2条第8項、第3条第2項、第4条第4項及び第6項、第5条第5項、第8条の2、第39条、第42条 |
| 改正年月日 | (公示)平成29年12月13日 政令第304号 |
| 施行日 | - |
| キーワード | |
| 改正の概要 | 平成29年法律第53号の改正規定の施行日が定められた。特定一般化学物質等に係る規定の施行日は平成31年1月1日、その他は、平成30年4月1日とされた。 |
| 法名 |
水銀による環境の汚染の防止に関する法律
|
|---|---|
| 改正条項 | 新用途水銀使用製品の製造等に関する命令第2条別表 |
| 改正年月日 | 平成29年10月16日 法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省告示第1号 |
| 施行日 | 一 |
| キーワード | |
| 改正の概要 | 水銀等による環境の汚染を防止するために、法律的な措置、その措置を実施するための国、地方公共団体、事業者及び国民の役割等が示された。 |
| 法名 |
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
|
|---|---|
| 改正条項 | 第12条の5、第12条の7、第14条の2、第14条の5、第15条の2の7、第17条の2、第19条の10、第27条の2 |
| 改正年月日 | 平成29年6月16日 法律第61号 |
| 施行日 | 原則として、平成29年10月1日、第12条の3、第12条の4、第12条の5、第12条の6、第19条の5第1項第3号の規定は、公布の日から起算して3年以内。 |
| キーワード | |
| 改正の概要 | ①市町村長、都道府県知事等は、許可を取り消された者、事業を廃止した者等が廃棄物の処理を完了していない場合に、これらの者に対して委託者への書面による通知等必要な措置を命ずること、②特定の産業廃棄物を多量に排出する事業者に対し、紙マニフェストの交付に代えて電子マニフェストの使用を義務付けること、③有害使用済機器等を保管又は処分を業として行う者に対し、都道府県知事への届出、処理基準等の義務付けの措置が講じられたこと、④認定を受けた親子会社は、廃棄物処理業の許可を受けないで、相互に親子会社間で産業廃棄物の処理を行うことができる特例が規定された。 |
| 法名 |
労働安全衛生法
|
|---|---|
| 改正条項 | 規則第95条の6 |
| 改正年月日 | 平成28年12月22日 厚生労働省告示第430号 |
| 施行日 | 平成29年1月1日から適用 |
| キーワード | |
| 改正の概要 | 事業場における労働者の有害物へのばく露による健康障害を防止するために、有害物ばく露作業についての報告が義務付けられる有害物として新た7物質が指定された。報告対象は、平成29年1月1日から同年12月31日までに一の事業場で製造し、又は取り扱った有害物が500kg 以上の事業者であり、報告期間は平成30年1月1日から同年3月31日とされた。 |
| 法名 |
PCB処理法
|
|---|---|
| 改正条項 | 第2条、第3条、第4条、第5条、第6条、第8条、第9条、第10条、第11条、第12条、第13条、第14条、第15条、第17条、第18条、第19条、第20条、第21条、第22条、第23条、第24条、第25条、第34条 |
| 改正年月日 | (公表)平成28年5月2日 法律第34号 |
| 施行日 | 公布の日から起算して3か月を超えない範囲内で政令で定める日 |
| キーワード | |
| 改正の概要 | -ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業者に対し、計画的処理完了期限より前の処分を義務付けし、義務違反に対しては改善命令ができ、命令違反には罰則が科されることとされた。使用中の高濃度PCB使用製品についても、所有事業者に対し、計画的処理完了期限より前に廃棄することを義務付けた。 -また、保管事業者が不明等の場合には、都道府県等は高濃度PCB廃棄物の処分に係る代執行を行うことができることとされた。さらに、PCB特措法に基づく届出がされていない高濃度PCB廃棄物等について、都道府県等による事業者への報告徴収や立入検査の権限が強化された。電気事業法の電気工作物に該当する高濃度PCB使用製品については、電気事業法によるとされた。 |
| 法名 |
食品リサイクル法
|
|---|---|
| 改正条項 | 食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令 別記様式、第9条第1項関係 |
| 改正年月日 | 平成25年9月11日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号 |
| 施行日 | 公布の日から施行 |
| キーワード | |
| 改正の概要 | 食品廃棄物等多量発生事業者の定期報告において、「食品廃棄物等の発生量及び食品循環資源の再生利用等の変化状況」及び食品関連事業者が目標の基準とする「基準実施率」の記載は、平成25年以降も記載することとなり、食品循環資源の再生利用等の実施率が基準実施率以下の場合は、その理由を記載することとなった。 |
| 法名 |
省エネルギー法
|
|---|---|
| 改正条項 | 法第1条〜法第3条、法第4条〜法第6条、法第16条、法第52条、法第53条、法第57条〜法第60条、法第64条、法第65条、法第70条、法第72条、法第77条〜法第80条、法第81条の2〜法第81条の7、法第86条 |
| 改正年月日 | 平成25年5月31日 法律第25号 |
| 施行日 | 公布の日から起算して1年3月を超えない政令で定める日。ただし、第2条は公布の日。 |
| キーワード | |
| 改正の概要 | 法の目的及び基本方針に、“電気の需要の平準化”の規定を新たに導入した。これに伴い、工場等、貨物輸送事業者、荷主、旅客輸送事業者に対して国は、“電気の需要の平準化”のための指針を定め、一定規模以上の事業者にはエネルギーの使用の合理化状況が判断の基準に照らして十分でない場合の勧告等の措置が規定された。機械器具については、エネルギー消費機器に対し、新たに、関係機器を含めたエネルギー使用の合理化を求め、政令で定める特定関係機器を定め、トップランナー制度の対象にしたこと、さらに、建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失防止建築材料(熱損失防止建築材料)の熱の損失の防止性能の向上、同建築材料の判断の基準となる事項を定めること、同建築材料のうち政令で定めるもの(特定熱損失防止建築材料)をトップランナー制度の対象としたこと、一般消費者への情報提供等が規定された。 |