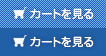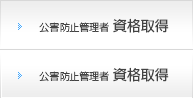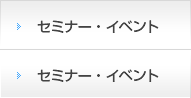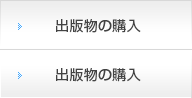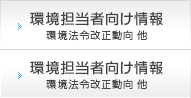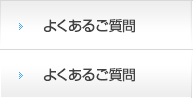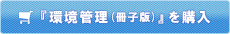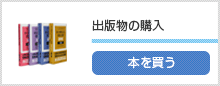- HOME
- 環境担当者向け情報 (JEMAI CLUB)
- 先読み環境法 -法改正の動向-
先読み環境法 -法改正の動向-
2024年7月
| PFHxS関連物質とPFOA関連物質の第一種特定化学物質追加について |
第246回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会等合同会合
令和6年度第4回薬事審議会化学物質安全対策部会化学物質調査会、令和6年度化学物質審議会第1回安全対策部会・第239回審査部会、第246回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会(以下、3省合同会合)が三部構成で開催された。会合はYoutubeで配信された。
| 概要 |
|---|
|
3省合同会合が7月19日(金)に三部構成で開催された。第一部ではPFHxS関連物質の第一種特定化学物質追加について、第二部は第一種特定化学物質に指定することが適当とされたデクロランプラスに係る所要の措置について、第三部では第一種特定化学物質であるペルフルオロオクタン酸関連物質に追加する物質について審議された。会合はYoutubeで配信された。
|
※取りまとめは本編集部によるものです。会員の方は「改正内容はこちら」より詳細をご確認いただけます。
|
【NO.145】GX 実現に向けた排出量取引制度の検討に資する法的課題研究会(経済産業省・環境省) 他
『機関誌:環境管理2024年7月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
経済産業省と環境省主催のGX実現に向けた排出量取引制度の検討に資する法的課題研究会が、2024年5月17日に第1回、6月5日に第2回が開催された。研究会の趣旨・目的、論点等について解説する。
| 1 | GX実現に向けた排出量取引制度の検討に資する法的課題研究会(経済産業省・環境省) |
|---|---|
| 2 | 第1回(5月27日)の排出量取引制度に係る憲法上の論点整理 |
| 3 | 第2回(6月5日)の排出量取引制度に係る行政法上の論点整理 |
【本編は「改正内容はこちら」 ヘ続く】
2024年6月
| PFHxS関連物質の第一種特定化学物質への指定について |
第245回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会等合同会合
第245回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会等合同会合が6月21日(金)開催された。議題として「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)対象物質の化学物質審査規制法第一種特定化学物質への指定について」が審議され、会合はYoutubeで配信された。
| 概要 |
|---|
|
ストックホルム条約COP10の結果を踏まえ、令和6年2月1日に「PFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩」が化審法第一種特定化学物質に追加された。COP10で同様にAnnex Aに追加されたPFHxS関連物質については、POPRC15で具体的な物質例示リストが作成されているものの、今後掲載物質に変更があり得ることに鑑み、条約の定義を引用した記述として政令に規定し、具体的な物質群は省令において別途指定することとされた。
|
※取りまとめは本編集部によるものです。会員の方は「改正内容はこちら」より詳細をご確認いただけます。
|
【NO.144】第六次環境基本計画の策定 他
『機関誌:環境管理2024年6月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
2024年2月26日の第115回中央環境審議会総合政策部会で案がまとめられた「第六次環境基本計画」について解説する。また、5月13日の第11回GX実行会議での総理発言についてまとめた。
| 1 | 第六次環境基本計画の策定 |
|---|---|
| 2 | 第六次環境基本計画(案) |
| 3 | 第六次環境基本計画の全体像 |
| 4 | 「ウェルビーイング/高い生活の質」をもたらす「新たな成長」の実現 |
| 5 | 5月13日の第11回GX実行会議での総理発言(GX移行戦略を国家戦略へ) |
【本編は「改正内容はこちら」 ヘ続く】
2024年5月
|
【パブリックコメント】「持続可能な窒素管理に関する行動計画(案)」に対する御意見の募集について(2024/5/24)
|
e-Govパブリックコメント/案件番号195240014
標記について、2024年5月24日から2024年6月23日まで意見募集が行われている。
| 意見募集内容 |
|---|
|
国連環境総会(UNEA)で2019年に採択された持続可能な窒素管理の決議を踏まえ、我が国において水・大気環境の保全・管理と、脱炭素、資源循環、自然共生との統合的アプローチにより、持続可能な窒素の管理によって社会や地域に貢献する取組を推進等するための「持続可能な窒素管理に関する行動計画(案)」について、意見の募集が行われている。
|
※取りまとめは本編集部によるものです。会員の方は「改正内容はこちら」より詳細をご確認いただけます。
|
【NO.143】海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案が3月12日に閣議決定、衆議院に提出 他
『機関誌:環境管理2024年5月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
3月12日に閣議決定、衆議院に提出された「再エネ海域利用法の一部を改正する法律案」について、3月15日閣議決定、同日衆議院に提出された「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律案」について、2月27日に閣議決定、同日衆議院に提出された「都市緑地法等の一部を改正する法律案」、「食料・農業・農村基本法の一部を改正する法律案」、「食料供給困難事態対策法案」及び「食料の安定供給のための農地の確保及びその有効な利用を図るための農業振興地域の整備に関する法律等の一部を改正する法律案」のについて、概要を解説する。また、2023年12月22日公表された「分野別投資戦略」についての補足、3月29日公表されたネイチャーポジティブ経済移行戦略の策定を解説する。
| 1 | 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法 律案が3月12日に閣議決定、衆議院に提出 |
|---|---|
| 2 | 3月15日、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律案が閣議決定され、同日、 衆議院に提出 |
| 3 | 都市緑地法等の一部を改正する法律案が2月27日に閣議決定、同日衆議院に提出 |
| 4 | 食料・農業・農村基本法の一部を改正する法律案、食料供給困難事態対策法案及び食料の安定供給 のための農地の確保及びその有効な利用を図るための農業振興地域の整備に関する法律等の一部を 改正する法律案が2月27日に閣議決定され、同日、衆議院に提出 |
| 5 | 2023年12月22日公表された「分野別投資戦略」 |
| 6 | ネイチャーポジティブ経済移行戦略の策定 ―3月29日公表 |
【本編は「改正内容はこちら」 ヘ続く】
2024年4月
|
【NO.142】水素社会推進法案及びCCS事業法案を2月13日に閣議決定、衆議院に提出 他
『機関誌:環境管理2024年4月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
2月13日に閣議決定、同日、衆議院に提出された「水素社会推進法案」及び「CCS事業法案」の概要と、3月7日の中央環境審議会「風力発電事業に係る環境評価の在り方(一次答申)」について、3月5日に閣議決定、同日、衆議院に提出された「地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律案」、「地球温暖化対策の促進に関する法律の一部を改正する法律案」について解説する。
| 1 | 水素社会推進法案及びCCS事業法案を2月13日に閣議決定、衆議院に提出 |
|---|---|
| 2 | 水素社会推進法案の概要(注:3月5日の経産省報道発表資料による) |
| 3 | 二酸化炭素の貯留事業に関する法律案(CCS事業法)の概要(注:3月5日の経産省報道発表資料による) |
| 4 | 3月7日の中央環境審議会の答申「風力発電事業に係る環境評価の在り方(一次答申)」について |
| 5 | 地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律案が3月5日に閣議決定、同日、衆議院に提出 |
| 6 | 地球温暖化対策の促進に関する法律の一部を改正する法律案が3月5日に閣議決定、同日、衆議院に提出 |
【本編は「改正内容はこちら」 ヘ続く】
2024年3月
|
【NO.141】CCS事業法の制定に向けて 他
『機関誌:環境管理2024年3月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
カーボンマネジメント小委員会(総合資源エネルギー調査会 資源・燃料分科会)と産業保安基本制度小委員会(産業構造審議会 保安・消費生活用製品安全分科会)との合同会合による「中間とりまとめ案(CCSに係る制度的措置の在り方について)」について、脱炭素成長型経済構造移行債(GX経済移行債)について、海底下CCS制度に係る中央環境審議会水環境・土壌農薬部会の報告(2024年1月12日)について解説する。
| 1 | CCS事業法の制定に向けて―カーボンマネジメント小委員会(総合資源エネルギー調査会 資源・燃料分科会)と産業保安基本制度小委員会(産業構造審議会 保安・消費生活用製品安全分科会)との合同会合による中間とりまとめ |
|---|---|
| 2 | 脱炭素成長型経済構造移行債(GX経済移行債)―クライメート・トランジション利付国債の発行と分野別投資戦略の策定 |
| 3 | 海底下CCS制度に係る中央環境審議会水環境・土壌農薬部会の報告(2024年1月12日) |
【本編は「改正内容はこちら」 ヘ続く】
2024年2月
|
【パブリックコメント】労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件(2024/2/28)
|
e-Govパブリックコメント/案件番号495230427
標記について、2024年2月28日から2024年3月28日まで意見募集が行われている。
| 意見募集内容 |
|---|
|
改正労働安全衛生規則第577条の2第2項において厚生労働大臣が定める濃度の基準以下にしなければならないとされている物質が67物質定められている。今般、「令和5年度化学物質管理に係る専門家検討会報告書」を踏まえ、新たに112物質について濃度基準値を定める等の所要の改正につき、意見募集が行われている。
|
※取りまとめは本編集部によるものです。会員の方は「改正内容はこちら」より詳細をご確認いただけます。
|
【パブリックコメント】化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針の一部を改正する件(案)に関する御意見の募集について(2024/2/28)
|
e-Govパブリックコメント/案件番号495230428
標記について、2024年2月28日から2024年3月28日まで意見募集が行われている。
| 意見募集内容 |
|---|
|
令和6年4月1日に施行される改正労働安全衛生規則第577条の2第2項により厚生労働大臣が定める濃度の基準以下にしなければならないとされている物質が定められており、当該濃度基準値の適用等に関する技術上の指針が労働安全衛生法第28条第1項に基づき定められている。今般、「令和5年度化学物質管理に係る専門家検討会報告書」を踏まえ、新たに119物質について、測定方法を追加するための所要の改正を行い、また、リスクの見積りの評価の方法をより明確にする等の所要の改正につき、意見募集が行われている。
|
※取りまとめは本編集部によるものです。会員の方は「改正内容はこちら」より詳細をご確認いただけます。
|
【NO.140】COP28の結果 他
『機関誌:環境管理2024年2月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
2023年11月30日から12月13日にドバイにおいて、開催されたCOP28の結果について解説する。また、2023年3月31日に策定された「グリーン社会の実現に向けた事業者等の活動に関する独占禁止法上の考え方」について解説する。
| 1 | COP28の結果 |
|---|---|
| 2 | 公正取引委員会の2023年3月31日策定「グリーン社会の実現に向けた事業者等の活動に関する独占禁止法上の考え方」 |
【本編は「改正内容はこちら」 ヘ続く】
2024年1月
|
【パブリックコメント】労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について(2024/1/17)
|
e-Govパブリックコメント/案件番号495230334
標記について、2024年1月17日から2024年2月15日まで意見募集が行われている。
| 意見募集内容 |
|---|
|
安衛法に基づく、立入禁止や退避等の「危険性」に係る関係省令(安衛法規則、ボイラー則、クレーン則、ゴンドラ則)について、危険性に関する保護対象を基本的に労働者に限定してきたところ、労働者以外の者についても必要な保護の対象とするための改正について、意見募集が行われている。
|
※取りまとめは本編集部によるものです。会員の方は「改正内容はこちら」より詳細をご確認いただけます。
|
【NO.139】自然再興の実現に向けた民間等の活動促進に関する小委員会の答申案 (2023年11月27日)他
『機関誌:環境管理2024年1月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
「2030年ネイチャーポジティブ(自然再興)」を実現するために取りまとめられた「自然再興の実現に向けた民間等の活動促進に関する小委員会の答申案(2023年11月27日)」について、また、再生可能エネルギーの主力電源化の切り札とされる洋上風力発電事業の環境配慮の確保等が諮問され、その一次答申となる「風力発電事業に係る環境影響評価の在り方について(一次答申)(案)(2023年11月6日)」について解説する。
| 1 | 自然再興の実現に向けた民間等の活動促進に関する小委員会の答申案(2023年11月27日) |
|---|---|
| 2 | 風力発電事業に係る環境影響評価の在り方について(一次答申)(案)―2023年11月6日の中央環境審議会総合政策部会風力発電に係る環境影響評価の在り方に関する小委員会(第1回)で提示 |
【本編は「改正内容はこちら」 ヘ続く】
2023年12月
|
【パブリックコメント】化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律におけるメトキシクロル、デクロランプラス及び UV-328 に係る措置(案)(2023/12/12)
|
e-Govパブリックコメント/案件番号595223066
標記について、2023年12月12日から2024年1月10日まで意見募集が行われている。
| 意見募集内容 |
|---|
|
「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」(以下「ストックホルム条約」という。)の附属書 A(廃絶)に追加することが決定されたメトキシクロル、デクロランプラス及びUV-328について、化審法の第一種特定化学物質に指定し、所要の措置を講じる案について、意見募集が行われている。
|
※取りまとめは本編集部によるものです。会員の方は「改正内容はこちら」より詳細をご確認いただけます。
|
【NO.138】食料・農業・農村政策審議会の答申(2023年9月11日)他
『機関誌:環境管理2023年12月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
食料・農業・農村政策審議会から現行の食料・農業・農村基本法の基本理念や主要施策等の見直しを求める答申について(2023年9月11日)、また、「再生可能エネルギー長期電源化・地域共生ワーキングループの第2次取りまとめ(案)」(2023年9月26日)、2023年8月31日に公表された「洋上風力発電の環境影響制度の最適な在り方に関する検討会の取りまとめ」について解説する。
| 1 | 食料・農業・農村政策審議会の答申(2023年9月11日) |
|---|---|
| 2 | 再生可能エネルギー長期電源化・地域共生ワーキングループの第2次取りまとめ(案)(2023年9月26日) |
| 3 | 「洋上風力発電の環境影響評価制度の最適な在り方について」を公表(2023年8月31日)―洋上風力発電の環境影響制度の最適な在り方に関する検討会の取りまとめ |
【本編は「改正内容はこちら」 ヘ続く】
2023年11月
|
【閣議決定】化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令について(2023/11/28)
|
化審法施行令改正の閣議決定について
標記結果が環境省より報道発表された。
| 報道発表の要点 |
|---|
|
ストックホルム条約第10回締約国会議(令和4年6月)の結果を踏まえ、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)第2条第2項に規定された第一種特定化学物質として、「PFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩」を指定すること等について、化審法施行令の改正を行うことについて閣議決定された。
|
※取りまとめは本編集部によるものです。会員の方は「改正内容はこちら」より詳細をご確認いただけます。
| 【中環審/循環型社会部会】静脈産業の脱炭素型資源循環システム構築に係る小委員会(第4回)(2023/11/22) |
脱炭素型資源循環システム構築に向けた論点整理について
標記小委員会が2023年11月22日に開催され、YouTubeで公開された。
| 議事内容 |
|---|
|
2023年4月のG7気候・エネルギー・環境大臣会合において採択されたCEREP(循環経済・資源効率性原則)を反映する政策として、資源循環を推進するための循環資源の国内市場整備、動静脈連携等が議論されている。第4回となる今回は、脱炭素型資源循環システム構築に向けた論点整理が行われた。
|
※取りまとめは本編集部によるものです。会員の方は「改正内容はこちら」より詳細をご確認いただけます。
プラスチック汚染に関する条約策定に向けたINC3の結果概要
| 報道発表の概要 |
|---|
|
2023年11月13日から11月19日まで、ケニア共和国・ナイロビにおいて、プラスチック汚染に関する法的拘束力のある国際文書(条約)の策定に向けた第3回政府間交渉委員会(INC3)が開催された。
|
※取りまとめは本編集部によるものです。会員の方は「改正内容はこちら」より詳細をご確認いただけます。
|
【その他】令和5年度「化学物質管理に係る専門家検討会」の中間取りまとめ公表(2023/11/21)
|
個人ばく露測定に係る測定精度を担保するための方策について
| 内容 |
|---|
|
昨年5月に公布された厚生労働省令第91号第5条により、改正労働安全衛生規則等による新たな化学物質規制が導入された。これを円滑に施行するため、個人ばく露測定に係る測定精度を担保するための方策について、化学物質管理に係る専門家検討会での議論を取りまとめたもの。精度担保の基本的な考え方や、資格者の要件などを整理するとともに、精度を担保するための仕組みが示されている。
|
※取りまとめは本編集部によるものです。会員の方は「改正内容はこちら」より詳細をご確認いただけます。
|
【パブリックコメント】「調整後温室効果ガス排出量を調整する方法の一部を改正する件(案)」に対する意見募集について(2023/11/17)
|
e-Govパブリックコメント/案件番号195230051
標記について、2023年11月17日から12月16日まで意見募集が行われている。
| 意見募集内容 |
|---|
|
調整後温室効果ガス排出量を調整する方法(平成22年経済産業省・環境省告示第4号)において、廃棄物の燃料利用又は廃棄物燃料の使用により発生する二酸化炭素の扱い等その他所要の改正を行う件について意見募集が行われている。
|
※取りまとめは本編集部によるものです。会員の方は「改正内容はこちら」より詳細をご確認いただけます。
|
【パブリックコメント】「輸出貿易管理令第4条第2項の規定に基づく経済産業大臣が告示で定める貨物」等の一部改正案に対する意見募集について(2023/11/11)
|
e-Govパブリックコメント/案件番号595123096
標記について、2023年11月11日から12月10日まで意見募集が行われている。
| 意見募集内容 |
|---|
|
輸出貿易管理令第4条第2項第2号イ、第3号及び第4号の経済産業大臣が告示で定める貨物等に「ペルフルオロ(ヘキサン-1-スルホン酸)(別名PFHxS)若しくはペルフルオロ(アルカンスルホン酸)(構造が分枝であって、炭素数が6のものに限る。)又はこれらの塩」を追加する件につき、意見募集が行われている。
|
※取りまとめは本編集部によるものです。会員の方は「改正内容はこちら」より詳細をご確認いただけます。
水俣条約COP5による水銀添加製品の規制の見直し
標記結果が環境省より報道発表された。
| 報道発表の要点 |
|---|
|
2023 年10 月30 日から同年11 月3日まで、スイス連邦・ジュネーブにおいて「水銀に関する水俣条約第5回締約国会議(COP5)」が開催された。COP5では、水銀添加製品の規制の見直しや規制の対象となる水銀汚染廃棄物のしきい値等に関する議論等が行われ、全ての蛍光ランプの製造等を、その種類に応じ2026 年末又は2027 年末までに禁止することが合意された。
|
※取りまとめは本編集部によるものです。会員の方は「改正内容はこちら」より詳細をご確認いただけます。
|
【NO.137】「成長志向型の資源自律経済戦略」のアクションである産官学CEパートナー シップの立ち上げと静脈産業の動脈産業との連携加速化に向けた制度整備他
『機関誌:環境管理2023年11月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
「成長志向型の資源自律経済戦略」のアクションである産官学CEパートナーシップの立ち上げと静脈産業の動脈産業との連携加速化に向けた制度整備の概要、それに伴う環境省の動向について解説する。また、経済産業省政策の新機軸である「成長志向型の資源自律経済戦略」や国際的な政策ダイナミズムの動き、EUの炭素中立型循環経済行動計画(2020年3月)についてさらに詳しく解説する。
| 1 | 「成長志向型の資源自律経済戦略」のアクションである産官学CEパートナーシップの立ち上げと静脈産業の動脈産業との連携加速化に向けた制度整備 |
|---|---|
| 2 | 環境省の動向 |
| 3 | 成長志向型の資源自律経済戦略 |
| 4 | 国際的な政策ダイナミズムの動き |
| 5 | EUの炭素中立型循環経済行動計画(2020年3月) |
【本編は「改正内容はこちら」 ヘ続く】
2023年10月
| 【中環審/循環型社会部会】静脈産業の脱炭素型資源循環システム構築に係る小委員会(第3回)(2023/10/26) |
情報を通じた動脈企業と静脈企業の連携等について
標記小委員会が2023年10月26日に開催され、YouTubeで公開された。
| 議事内容 |
|---|
|
2023年4月のG7気候・エネルギー・環境大臣会合において採択されたCEREP(循環経済・資源効率性原則)を反映する政策として、資源循環を推進するための循環資源の国内市場整備、動静脈連携等が議論されている。第3回となる今回の小委員会では、静脈産業の脱炭素型資源循環システム構築等が議論された。
|
※取りまとめは本編集部によるものです。会員の方は「改正内容はこちら」より詳細をご確認いただけます。
|
【パブリックコメント】「液化石油ガス保安規則の一部を改正する省令案」等に対する意見募集について(2023/10/12)
|
e-Govパブリックコメント/案件番号595123075
標記について、2023年10月12日から11月10日まで意見募集が行われている。
| 意見募集内容 |
|---|
|
高圧ガス保安法等の一部を改正する法律において、新たに「認定高度保安実施者制度」を措置したことから、同法の施行に伴い、その具体的要件等を整備する必要があるため、関係省令の整備を行う。
|
※取りまとめは本編集部によるものです。会員の方は「改正内容はこちら」より詳細をご確認いただけます。
|
【パブリックコメント】労働安全衛生規則及びボイラー及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について(2023/10/10)
|
e-Govパブリックコメント/案件番号495230182
標記について、2023年10月10日から11月8日まで意見募集が行われている。
| 意見募集内容 |
|---|
|
ボイラーについては、労働安全衛生法第14条に基づきボイラー取扱作業主任者を選任しなければならない等、伝熱面積に応じた規制が定められている。令和5年に、電気ボイラーは燃焼式ボイラーと安全性が同程度であることから、電気ボイラーについての規制が同等の能力を有する燃焼式ボイラーについての規制と同等となるよう見直すべきとの提案が産業界よりなされた。これを踏まえ、電気ボイラーの伝熱面積の算定方法について、同等の能力を有しつつ、安全性が適切に確保されている燃焼式ボイラーの基準に合わせるための改正等について、意見募集が行われている。
|
※取りまとめは本編集部によるものです。会員の方は「改正内容はこちら」より詳細をご確認いただけます。
|
【パブリックコメント】容器保安規則の一部を改正する省令案等に対する意見公募要領について(2023/10/6)
|
e-Govパブリックコメント/案件番号595123074
標記について、2023年10月6日から11月4日まで意見募集が行われている。
| 意見募集内容 |
|---|
|
高圧ガス保安法等の一部を改正する法律において、新たな適用除外の対象として道路運送車両法に規定する運行の用に供する自動車の装置内における高圧ガスが規定されたことを踏まえ、関係省令・告示等の改正を行う。また、有識者・関係業界団体等による審議等を踏まえ、規制改革実施計画に掲げられた圧縮水素スタンドに関する規制見直し項目に関する見直し等も行う。これらについて、意見募集が行われている。
|
※取りまとめは本編集部によるものです。会員の方は「改正内容はこちら」より詳細をご確認いただけます。
|
【パブリックコメント】「特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令の一部を改正する省令(案)」に対する意見募集について(2023/10/5)
|
e-Govパブリックコメント/案件番号195230030
標記について、2023年10月5日から11月3日まで意見募集が行われている。
| 意見募集内容 |
|---|
|
地球温暖化対策の推進に関する法律第26条第1項に基づき事業者が事業所管大臣に報告する「温室効果ガス算定排出量」の算定方法に関し、特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令(平成18年経済産業省・環境省令第3号)について所要の改正を行う。
|
※取りまとめは本編集部によるものです。会員の方は「改正内容はこちら」より詳細をご確認いただけます。
|
【NO.136】『第53回総合資源エネルギー調査会基本政策分科会開催、GX推進戦略を閣議決定、第7回GX実行会議での総理発言』他
『機関誌:環境管理2023年10月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
第53回総合資源エネルギー調査会基本政策分科会開催、GX推進戦略を閣議決定、第7回GX実行会議での総理発言について、さらに、第6次生物多様性国家戦略における生物多様性と企業の事業活動について解説する。また、2022年4月1日施行された「プラスチック使用製品設計指針」の内容やプラスチック資源循環法に含まれている修理する権利、欧州グリーンディール、気候中立と循環経済の両立を目指す循環経済行動計画についても解説する。
| 1 | 第53回総合資源エネルギー調査会基本政策分科会開催、GX推進戦略を閣議決定、第7回GX実行会議での総理発言 |
|---|---|
| 2 | 第6次生物多様性国家戦略における生物多様性と企業の事業活動 |
| 3 | プラスチック使用製品設計指針 |
| 4 | 修理する権利 |
| 5 | 欧州グリーンディール(本号)、気候中立と循環経済の両立を目指す循環経済行動計画(次号) |
【本編は「改正内容はこちら」 ヘ続く】
2023年9月
|
【パブリックコメント】危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(案)等に対する意見公募について(2023/09/26)
|
e-Govパブリックコメント/案件番号860202302
標記について、2023年9月26日から10月25日まで意見募集が行われている。
| 意見募集内容 |
|---|
|
危険物の規制に関する政令、危険物の規制に関する規則、危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和49年自治省告示第99号)の改正案について意見公募(パブリックコメント)が行われている。
|
※取りまとめは本編集部によるものです。会員の方は「改正内容はこちら」より詳細をご確認いただけます。
|
【パブリックコメント】「水質汚濁防止法に基づく排出水の排出の規制に係る基準等の見直しについて(報告案)」に関する意見募集について(2023/09/20)
|
e-Govパブリックコメント/案件番号195230025
標記について、2023年9月20日から10月19日まで意見募集が行われている。
| 意見募集内容 |
|---|
|
公共用水域の水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の項目(生活環境項目)である大腸菌群数については、より的確にふん便汚染を捉えることができる指標である大腸菌数に項目の改正が行われた。これを踏まえ、環境省において「大腸菌群数の排水基準等の見直しに係る検討会」を設置して検討し、その結果を踏まえ、中央環境審議会への報告案が取りまとめられた。本パブリックコメントは、この報告案に対する意見募集。
|
※取りまとめは本編集部によるものです。会員の方は「改正内容はこちら」より詳細をご確認いただけます。
|
【パブリックコメント】「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)」に関する意見募集について(2023/9/15)
|
e-Govパブリックコメント/案件番号595123070
標記について、2023年9月15日から10月14日まで意見募集が行われている。
| 意見募集内容 |
|---|
|
PFHxSとその塩及びPFHxS関連物質を廃絶対象物質とすることを決定したストックホルム条約COP10の結果を反映して、「PFHxS又はこれらの塩若しくはその異性体又はこれらの塩」の化審法第一種特定化学物質への追加、及びこれらが使用されている場合に輸入することができない製品の化審法施行令追加について、意見募集が行われている。
|
※取りまとめは本編集部によるものです。会員の方は「改正内容はこちら」より詳細をご確認いただけます。
|
【パブリックコメント】「労働安全衛生法施行令第18条第3号及び第18条の2第3号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準(案)」に関する意見募集について(2023/09/05)
|
e-Govパブリックコメント/案件番号495230147
標記について、2023年9月5日から10月4日まで意見募集が行われている。
| 意見募集内容 |
|---|
|
労働安全衛生法施行令第18条第3号及び第18条の2第3号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準(ラベル表示に関わる裾切値とSDS交付に係る裾切値)について、意見募集が行われている。
|
※取りまとめは本編集部によるものです。会員の方は「改正内容はこちら」より詳細をご確認いただけます。
|
【NO.135】『COP15「昆明・モントリオール生物多様性枠組」と第6次「生物多様性国家戦略2023-2030」』他
『機関誌:環境管理2023年9月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
COP15で採択された「昆明・モントリオール生物多様性枠組」、これを受けて第6次「生物多様性国家戦略2023-2030」が閣議決定された。「昆明・モントリオール生物多様性枠組」の23項目のターゲットの内容と第6次生物多様性国家戦略の5つの基本戦略について解説する。また、「ネイチャーポジティブ」について詳しく解説する。
| 1 | COP15「昆明・モントリオール生物多様性枠組」と第6次「生物多様性国家戦略2023-2030」 |
|---|---|
| 2 | 「昆明・モントリオール生物多様性枠組」の23項目のターゲットの内容 |
| 3 | 第6次生物多様性国家戦略の5つの基本戦略それぞれの状態目標・行動目標 |
| 4 | ネイチャーポジティブ |
【本編は「改正内容はこちら」 ヘ続く】
2023年8月
|
【パブリックコメント】リスクアセスメント対象物健康診断に関するガイドライン(案)に関する御意見の募集について(2023/8/18)
|
e-Govパブリックコメント/案件番号495230133
標記について、2023年8月18日から9月1日まで意見募集が行われている。
| 意見募集内容 |
|---|
|
労働安全衛生規則第577条の2第3項及び第4項に規定するリスクアセスメント対象物健康診断の趣旨・目的を正しく理解し、その適切な実施が図られるよう、基本的な考え方及び留意すべき事項を示した「リスクアセスメント対象物健康診断に関するガイドライン(案)」について、意見募集が行われている。
|
※取りまとめは本編集部によるものです。会員の方は「改正内容はこちら」より詳細をご確認いただけます。
|
【中央環境審議会】「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置について(第一次答申)」及び「同(第二次答申)」について(2023/8/7)
|
残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約新規対象物質の化学物質審査規制法第一種特定化学物質への指定について
標記について、中央環境審議会長から環境大臣に対し、以下のように答申がなされた。
| 答申内容 |
|---|
|
令和4年6月開催されたストックホルム条約第10回締約国会議の附属書改正により、条約の対象に追加された物質群(ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)とその塩及びPFHxS関連物質)の物質群について、化審法第2条第2項に規定する第一種特定化学物質への指定に係る審議が行われた。その結果、当該物質群を第一種特定化学物質に指定することが適当であるとの結論が出された。
|
※取りまとめは本編集部によるものです。会員の方は「改正内容はこちら」より詳細をご確認いただけます。
|
【NO.134】『許可の性格、規律構造からみた発電用原子炉の運転期間・延長期間、 劣化管理に係る電事法、炉規法の改正』他
『機関誌:環境管理2023年8月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より |
前号1、2に続く、3となる「許可の性格、規律構造からみた発電用原子炉の運転期間・延長期間、劣化管理に係る電事法、炉規法の改正」について、「7月1日に実施された水・大気環境局の組織再編」と2023年6月30日に意見具申された「今後の水・大気環境行政の在り方について」、また、「束ね法案の問題性―審議の形骸化と国会の決定権の縮小」について解説する。
| 1 | 許可の性格、規律構造からみた発電用原子炉の運転期間・延長期間、劣化管理に係る電事法、炉規法の改正(前号1、2に続く3) |
|---|---|
| 2 | 7月1日に実施された水・大気環境局の組織再編 |
| 3 | 今後の水・大気環境行政の在り方について(意見具申)2023年6月30日 |
| 4 | 束ね法案の問題性?審議の形骸化と国会の決定権の縮小 |
【本編は「改正内容はこちら」 ヘ続く】