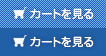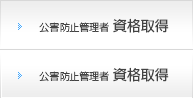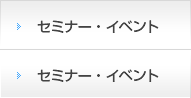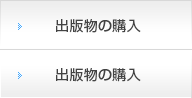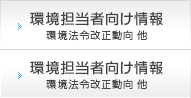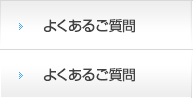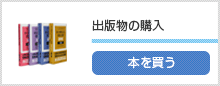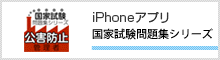- HOME
- 出版物の購入・ご案内
- 環境管理バックナンバー
- 検索結果
検索結果
記事を検索
キーワードで記事の検索ができます(例:GX カーボンプライシング)
バックナンバーの閲覧 / 冊子版の購入
- 協会会員の方は、記事全文をPDFファイルで閲覧ができます。
ログインしてご利用ください。 - 各号の概要の閲覧、冊子版の購入はどなたでも
ご利用いただけます。
キーワード「ナノ」が付けられているもの
-
<総説>科学技術基本計画によるナノテクノロジー・材料分野の研究開発の推進について --第3期(H18〜22)の総括的フォローアップより
只見康信 東京大学サステイナビリティ学連携研究機構特任研究員(前内閣府企画官) ▼概要文表示2012年3月号 -
ナノテクノロジー・材料分野の科学技術は,環境・エネルギー問題などの解決に資するキーテクノロジー(基盤技術)として注目を集める。政府の総合科学技術会議は,第3期科学技術基本計画(H18~22)により, 1)ナノエレクトロニクス,2)ナノバイオテクノロジー・生体材料,3)材料,4)ナノテクノロジー・材料分野推進基盤,5)ナノサイエンス・物質科学の5領域を推進してきた。本稿では,環境管理関連を含む研究開発の成果を解説するものだが,こうした成果の社会還元が,将来のイノベーションへの貢献を通じて期待される。
-
<総説>工業ナノ材料の安全性問題の動向(その3)
五十嵐卓也 独立行政法人産業技術総合研究所安全科学研究部門主任研究員 ▼概要文表示2011年4月号 -
工業ナノ材料の産業応用の急速な進展に伴い,既存の化学物質管理法令がこの状況に対応できていないために,その安全性への懸念が高まっている。シリーズの第1回目(先々月号)では,工業ナノ材料の安全性問題に関する最近の状況を概観し,我が国政府機関の取組を紹介した。第2回目(先月号)では,OECD/WPMN,ISO/TC 229等の国際機関の取組を紹介した。本稿では,欧州連合の取組を紹介し,次回第4回では,米国等の取組を紹介するとともに,今後を展望する。
-
<総説>工業ナノ材料の安全性問題の動向(その2)
五十嵐卓也 独立行政法人産業技術総合研究所安全科学研究部門主任研究員 ▼概要文表示2011年3月号 -
工業ナノ材料の産業応用の急速な進展に伴い,既存の化学物質管理法令がこの状況に対応できていないために,その安全性への懸念が高まっている。3回シリーズの第1回目(先月号)では,工業ナノ材料の安全性問題に関する最近の状況を概観し,我が国政府機関の取組を紹介した。本稿ではOECD/WPMN,ISO/TC229等の国際機関の取組を紹介し,第3回目では欧州連合,米国等の取組を紹介するとともに,今後を展望する。
-
<総説>工業ナノ材料の安全性問題の動向(その1)
五十嵐卓也 独立行政法人産業技術総合研究所安全科学研究部門主任研究員 ▼概要文表示2011年2月号 -
工業ナノ材料の産業応用の急速な進展に伴い,既存の化学物質管理法令がこの状況に対応できていないために,その安全性への懸念が高まっている。本稿では,工業ナノ材料の安全性問題に関する最近の状況を概観した上で,我が国政府機関の取組を紹介し,第2回目にOECD/WPMN,ISO/TC229等の国際機関の取組,第3回目に欧州連合,米国等の取組を紹介するとともに,今後を展望する。
-
<総説>日本および米国におけるナノリスク規制-その背景
小林 剛 環境医学情報センター・代表 ▼概要文表示2009年3月号 -
ナノテクノロジーに対する規制は,これまで各国とも政府のガイドラインや企業の自主管理による取り組みに委ねられてきたが,米国環境保護庁(US EPA)は,2008年1月より実施していたナノ企業による自主報告制度の「ナノスケール物質スチュワードシッププログラム」(NMSP: Nanoscale Materials Stewardship Program)では実効が挙がらないとの判断に加えて,ナノ物質の有害性研究の成果の蓄積により,同年10月,ナノ物質の代表的製品のカーボンナノチューブ(CNT)を,ついに有害物質規制法(TSCA:Toxic Substances Control Act)の「新規」化学物質と指定し,メーカーに対して正式届出の規制を課した。さらに11月には,ナノ粒子類に「重要新規使用規則」(SNUR)を適用,商業目的で製造・輸入・加工する場合には,少なくともその90日前にEPAへの届出を義務づけ,2009年4月の施行を決定した。これを契機に,今後,米国が先鞭をつけたナノ規制の動向は世界的に波及すると推測される。